【3分で完全理解】相続の基本ルール→知らないと100万円損する5つのポイント
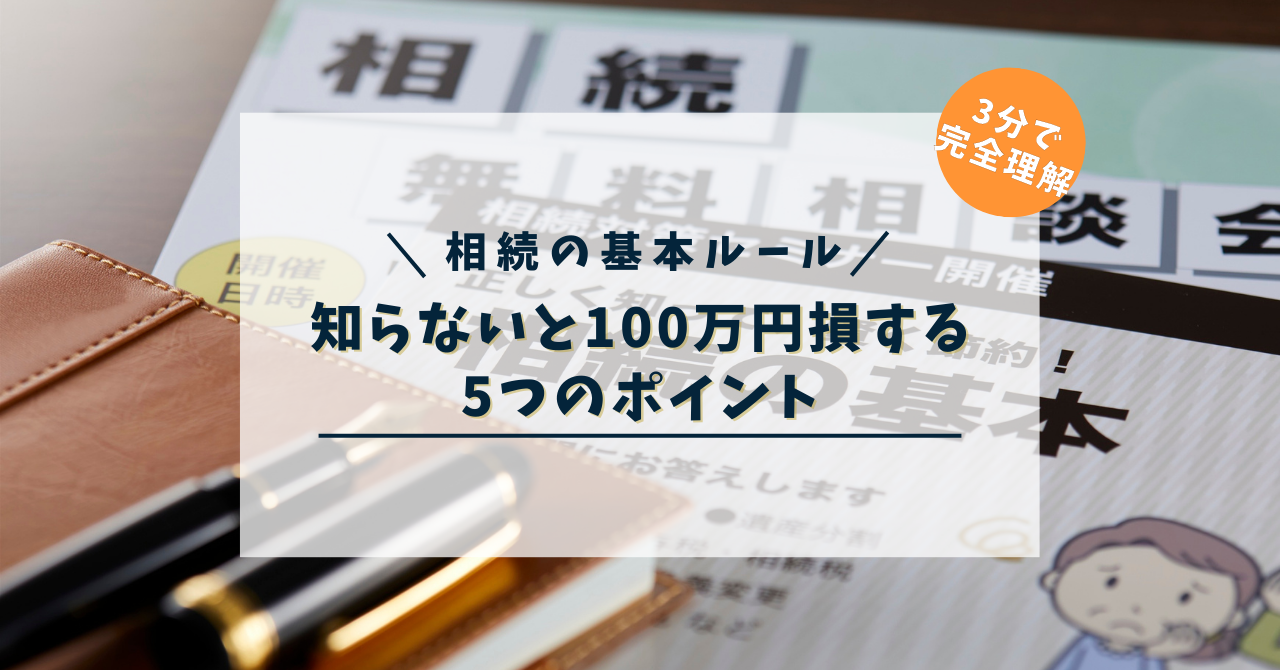

「相続なんて、ウチは財産家じゃないし、まだ先の話」
そう思っていませんか?
弊社では15年以上相続の相談をたくさんのご家庭から頂いておりますが、その経験から断言できることがあります。
それは、
「ウチは財産家じゃないから大丈夫」という思い込みこそが、一番キケンだ
ということです。
弊社には「もっと早く知っていれば…」「まさかウチがこんなことになるなんて…」という後悔の声が、今でも毎月たくさん届いています。
しかし、財産の多い少ないにかかわらず、相続をめぐる家族のトラブル(「争続」と呼んでいます)は、どこにでも起こり得ます。
- 「親の介護を私だけがやったのに、兄弟と同じ取り分なんて納得いかない!」
- 「実家(不動産)はあるけど、現金がない。どうやって分ければいいんだ…」
- 「親が亡くなった後、借金があることが分かった…」
こうした事態は、ほんの少しの「基本ルール」を知っているだけで、その多くが防げます。
この記事では、相続について考え始めた30代~50代の現役世代のあなたに向けて、難しい法律用語を一切使わずに「これだけは押さえて!」という5つの基本ルールを、具体的なご家庭の例を交えながら徹底的に解説します。
この記事を読み終えるころには、「なるほど、そういうことだったのか!」とスッキリし、今すぐ何をすべきかが明確になっているはずです。知っているだけで、将来的に100万円単位で損をしないための、大切なお金と家族の守り方。ぜひ、リラックスして読んでみてください。
🧐 相続の「基本ルール」とは? まずはココだけ押さえましょう
そもそも「相続」とは何でしょうか?
ものすごく簡単に言えば、
「亡くなった方(被相続人)の財産や借金を、特定の人(相続人)が受け継ぐこと」です。
ここで大事なのは、プラスの財産(預貯金、不動産、株など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)もセットで受け継ぐということです。
「じゃあ、その『特定の人』って誰?」「どれくらい受け継ぐの?」
それを決めるための交通整理役が、国が決めた「基本ルール(=民法)」です。
なぜルールが必要かというと、ルールがないと「私が一番お世話したから多くもらうべきだ」「いや、長男だから全部オレのものだ」と、収集がつかなくなってしまうからですね。
🗨️ よくある誤解:「ウチは揉めるほど財産がない」は本当?
弊社がたくさんの相続相談で見てきた中で、最も多い誤解がこれです。



「ウチは、都内の一等地にビルを持っているわけでもないし、ただのサラリーマン家庭。相続なんて関係ないよ」
これは大きな間違いです。
裁判所が公表しているデータ(令和4年司法統計)を見ても、相続トラブルで裁判所(家庭裁判所)に持ち込まれたケースのうち、遺産総額5,000万円以下のごく一般的なご家庭が、全体の77%以上を占めているんです。
なぜでしょう?
理由は、財産が「分けにくい」からです。
例えば、財産が「現金1億円」なら、法定相続人2人(兄弟)で5,000万円ずつ分ければスッキリ終わります。
しかし、ごく一般的なご家庭の財産が「評価額3,000万円の実家」と「現金500万円」だったらどうでしょう?
- 兄:「オレが実家を継ぐ。お前には現金をやる」
- 弟:「待てよ。実家が3,000万円で現金500万円じゃ不公平だ!」
- 兄:「でも実家を売ったら、お母さんが住む場所がなくなるぞ!」
…ほら、もうトラブルの匂いがプンプンしますよね。
だからこそ、財産の額にかかわらず、すべてのご家庭に「基本ルール」の知識が必要なんです。
💰 知らないと100万円損する!相続の基本ルール5選
お待たせしました。では、これだけは絶対に知っておいてほしい「5つの基本ルール」を見ていきましょう。
ここでは、ごく平均的な「田中家」をモデルケースにしてご説明します。
【モデルケース:田中家】
- お父さん(75歳): 元会社員。年金暮らし。
- お母さん(72歳): 専業主婦。
- 長男・太郎さん(45歳): 会社員(今回のターゲット読者)。既婚・子2人。
- 長女・花子さん(43歳): パート。既婚・子1人。
- 主な財産:
- 自宅(土地・建物):評価額 2,500万円
- 預貯金:1,000万円
- 財産合計:3,500万円
➡️ ポイント①:誰がもらえるの?「法定相続人」の決まり
まず最初のルールは、「誰が相続する権利を持っているか?」を決めるルールです。これを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と呼びます。
これは厳格に決まっています。
- 配偶者(夫・妻):常に法定相続人になります。
- 血族(血のつながりのある人):こちらは優先順位があります。
【血族の優先順位】
- 第1順位: 子ども(や孫)
- 第2順位: 親(や祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(や甥・姪)
ポイントは、
「先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になれない」ということです。
<田中家の場合>
もし、お父さんが亡くなった場合、法定相続人は誰でしょう?
- 配偶者: お母さんは「常に」相続人です。
- 血族: 第1順位の「子ども」(太郎さん・花子さん)がいます。
したがって、法定相続人は「お母さん、太郎さん、花子さん」の3人です。
お父さんの親(第2順位)や兄弟(第3順位)は、相続人にはなれません。
⚠️ ここで失敗する人が多いんです
- 「長男の嫁が、義理の親であるお父さんをずっと介護していた」
- 「内縁の妻(籍を入れていないパートナー)が長年連れ添った」
どんなに貢献しても、どんなに仲が良くても、「嫁」や「内縁の妻」は法定相続人ではありません。 1円も相続する権利がないのです。
こうした方に財産を残したい場合は、必ず「遺言書」が必要になります。
➡️ ポイント②:どれくらいもらえるの?「法定相続分」のキホン
相続人が決まったら、次は「それぞれの取り分」です。
これも法律で目安が決まっています。これを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と呼びます。
組み合わせで覚えるのがカンタンです。
- 配偶者 + 子ども(第1順位)
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2 (子どもが複数いれば、この1/2を人数で均等に割る)
- 配偶者 + 親(第2順位)
- 配偶者:2/3
- 親:1/3
- 配偶者 + 兄弟(第3順位)
- 配偶者:3/4
- 兄弟:1/4
<田中家の場合>
法定相続人は「お母さん、太郎さん、花子さん」の3人(配偶者+子ども2人)でしたね。
財産は合計3,500万円です。
- お母さん(配偶者): 1/2
- → 3,500万円 × 1/2 = 1,750万円
- → 3,500万円 × 1/2 = 1,750万円
- 子ども(太郎さん・花子さん): 全体で1/2
- この1/2を2人で均等に分けるので、1人あたりは 1/2 × 1/2 = 1/4
- 太郎さん: 3,500万円 × 1/4 = 875万円
- 花子さん: 3,500万円 × 1/4 = 875万円
これが法律上の「目安」となります。
⚠️ 注意!これは「目安」です
あくまで、遺言書がなく、相続人全員で話し合う(これを遺産分割協議といいます)場合の「目安」です。
全員が「お母さんの老後が心配だから、お母さんが全部もらってよ」と合意すれば、お母さんが3,500万円すべてを相続してもOKです。
しかし、この目安があることで、「私は法律通り875万円もらわないと納得しない!」と主張する権利が、花子さんにも太郎さんにもある、ということです。
➡️ ポイント③:遺言があっても最低限もらえる!「遺留分」とは?



「遺言書があれば、法定相続分なんて関係ないんでしょ?」
そう思った方、半分正解で半分間違いです。
確かに、遺言書は法定相続分よりも優先されます。「全財産を長男に」と書いてあれば、原則そうなります。
しかし、法律は「残された家族の生活も守るべきだ」と考えています。
そこで登場するのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
これは、「遺言書の内容にかかわらず、特定の相続人に最低限保証される財産の取り分」**のことです。
- 遺留分を主張できる人: 配偶者、子ども(第1順位)、親(第2順位)
- 遺留分を主張できない人: 兄弟姉妹(第3順位)
<田中家の場合>
もし、お父さんが「全財産3,500万円を、長男の太郎に相続させる」という遺言書を書いていたとします。
このままでは、お母さんと花子さんの取り分はゼロです。
しかし、2人には「遺留分」を主張する権利があります。
- 遺留分の額: ざっくり言うと「法定相続分の半分」です。
- お母さんの遺留分:
- 法定相続分は 1/2 (1,750万円)
- 遺留分はその半分の 1/4 (875万円)
- 花子さんの遺留分:
- 法定相続分は 1/4 (875万円)
- 遺留分はその半分の 1/8 (437.5万円)
お母さんと花子さんは、太郎さんに対して「遺留分が侵害されているので、その分のお金(合計1,312.5万円)を払ってください」と請求することができます。
最も重要な落とし穴です。遺留分は、相続が始まったことを知った時から1年以内に、「私に遺留分をください」と内容証明郵便などでキッチリ意思表示(請求)をしないと、時効で消えてしまいます。
黙っていたら、1円ももらえずに終わってしまうのです。
➡️ ポイント④:ウチはかかる?「相続税」とかからない「基礎控除」
さて、皆さんが一番気になるところ「相続税」です。
「相続=高い税金」というイメージがあるかもしれませんが、ほとんどのご家庭では相続税はかかりません。
なぜなら、「基礎控除(きそこうじょ)」という、非常に強力な非課税枠があるからです。
財産がこの基礎控除の金額以下であれば、相続税は1円もかからず、税務署への申告も不要です。
【相続税の基礎控除 算出式】
3,000万円 + (600万円 ×法定相続人の数)
この式だけは、絶対に覚えてください。
<田中家の場合>
お父さんの財産は3,500万円でした。
法定相続人は「お母さん、太郎さん、花子さん」の3人です。
基礎控除額を計算してみましょう。
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
- 田中家の財産:3,500万円
- 基礎控除額:4,800万円
財産(3,500万円)が基礎控除額(4,800万円)を下回っていますね。
したがって、田中家は相続税が一切かからない、ということになります。
一般的に年収500万~1,500万円のご家庭で、親御さんの財産が「実家+預貯金」という場合、この基礎控除内に収まるケースが非常に多いのです。
💡 2024年からの法改正(最新情報)
「生前贈与」について、ルールが少し変わりました。
以前は、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産にカウントバックされていましたが、2024年1月1日以降の贈与からは、カウントバックされる期間が7年に延長されました。
「相続税対策で早めに贈与しよう」と考えている方は、より長期的・計画的に進める必要が出てきた、ということです。
➡️ ポイント⑤:意外と時間がない!守るべき「手続き期限」
最後は「期限」です。
親が亡くなった後は、悲しむ間もなく、様々な手続きに追われます。
特に、以下の3つの期限は絶対に守ってください。守らないと、文字通り「100万円損する」ことになりかねません。
[1] 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認
「プラスの財産より、借金の方が多かった!」という場合に、すべての相続を放棄(相続放棄)するか、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返す(限定承認)手続きです。
家庭裁判所への申述が必要で、原則3ヶ月しかありません。
これを逃すと、親の借金をすべて背負うことになってしまいます。
[2] 4ヶ月以内:準確定申告(じゅんかくていしんこく)
亡くなった方が自営業者だったり、不動産収入があったりした場合に、亡くなった年(1月1日~亡くなった日)の所得税の申告をする手続きです。
[3] 10ヶ月以内:相続税の申告・納付
これが最重要です。
ポイント④で計算した基礎控除を「超える」場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。
⚠️ 10ヶ月をナメてはいけない!
「10ヶ月もある」と思ったら大間違いです。
- 戸籍謄本をすべて集める
- 不動産の評価額を計算する
- 預貯金をすべての銀行で洗い出す
- 誰が何を相続するか、全員で話し合って合意する(遺産分割協議)
これらをすべて終えて、やっと申告書が作れます。10ヶ月はあっという間です。
もし10ヶ月を過ぎると、延滞税などのペナルティがかかります。
それ以上に怖いのが、
相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例(実家の土地の評価を最大80%オフする)」といった強力な特例があるのですが、これらは「10ヶ月以内に申告すること」が適用の条件になっていることが多いのです。
この特例が使えないと、納税額が数百万、数千万円単位で跳ね上がることがあります。
まさに**「期限を知らないだけで100万円(以上)損する」典型的なパターンです。
🏃 「基本ルール」が分かったら、次は何をすべき?
さて、5つの基本ルールが頭に入ったところで、「じゃあ、ウチもそろそろ何か始めないと…」と感じた方も多いと思います。
でも、いきなり「お父さん、遺言書書いてよ!」と言うのはハードルが高いですよね(笑)。
私がいつもお勧めしている、現実的な3つのステップをご紹介します。
➡️ ステップ1:まずは「現状把握」から
何事も、敵(?)を知ることからです。
いきなり対策を考えるのではなく、まずは「もし今、相続が起きたら、ウチはどうなる?」をシミュレーションしてみましょう。
A:何を相続するのか?(財産リスト)
親御さんに直接聞くのが難しければ、まずはあなたが知っている範囲で書き出してみましょう。
- プラスの財産:
- 不動産(実家など)
- 預貯金(どの銀行にありそうか?)
- 有価証券(株や投資信託)
- 生命保険
- マイナスの財産:
- ローン(住宅ローン、車のローン)
- 借金(あるかないか?)
B:誰が相続するのか?(相続人マップ)
ポイント①でやった「法定相続人」の確認です。
家系図をカンタンに書いてみると、意外な人が相続人(例えば、会ったこともない腹違いの兄弟など)になる可能性に気づくこともあります。
➡️ ステップ2:家族と「軽く」話してみる
現状が把握できたら、次は「家族会議」…と言いたいところですが、そんなに重く構える必要はありません。
タイミングが重要です。
法事やお正月など、親戚が集まる時ではなく、ご両親とあなた(たち夫婦)だけでリラックスして話せる時を狙いましょう。
【切り出し方トーク例】
「そういえば、この前ネットで相続の記事を読んだんだけどさ。ウチって、実家とかどうするつもり? お父さんたち、何か考えてることある?」
ポイントは、「財産をよこせ」というスタンスではなく、「お父さんたちの想い(意思)を聞かせてほしい」というスタンスで聞くことです。
「お母さんがこの家に住み続けたいのか」「売ってマンションに移りたいのか」「将来、介護が必要になったら費用はどう考えているのか」…
こうした「想い」を聞き出すことが、将来の「争続」を防ぐ最大のカギになります。
➡️ ステップ3:「専門家」に壁打ち相手になってもらう
ステップ1と2を自分でやろうとしても、なかなか難しいものです。
「親に財産の話なんて、やっぱり切り出せない…」
「聞いたら、なんか機嫌が悪くなっちゃった…」
当たり前です。家族だからこそ、お金の話は感情的になりやすいんです。
そんな時こそ、私たちのような第三者の専門家を使ってください。
専門家というと、弁護士や税理士を思い浮かべるかもしれませんが、彼らは「トラブルが起きた後」や「相続税が確定した後」のプロです。
その手前の、「ウチの場合、何から手をつければいい?」「どうやって家族で話を進めればいい?」という、一番最初の「交通整理」をするのが、実は弊社のような保険代理店やFP(ファイナンシャルプランナー)の得意分野なんです。
私たち相続のプロは、あなたの家の「かかりつけ医」のようなものだと思ってください。
まずは全体をヒアリングして、「あ、これは相続税が心配だから税理士さんにつなぎますね」「これは揉めそうだから弁護士さんに遺言書を作ってもらいましょう」「納税資金が足りなさそうなので、保険で準備する方法もありますよ」と、最適な専門家へつなぐハブの役割を果たします。
いきなり税理士事務所のドアを叩くのは勇気がいりますが、私たちになら「ちょっと教えて」と気軽に聞けるはずです。
🙋 相続のよくあるギモン Q&A
最後に、これまで数多くの相談の中で、特によく聞かれた質問を3つピックアップしてお答えします。
- Q1:遺言書は、やっぱり書いたほうがいいですか?
-
法律上、必須ではありません。しかし、「相続トラブルの特効薬」として、ほとんどすべての方に書くことをお勧めしています。特に、以下に一つでも当てはまる方は、絶対に書くべきです。
- 子どもがいないご夫婦(→親や兄弟も相続人になり、話が複雑になるため)
- 「嫁」や「内縁の妻」など、法定相続人以外の人に財産をあげたい
- 特定の相続人に多く財産を渡したい(例:長男に事業を継がせる)
- 相続人同士の仲があまり良くない
遺言書は、お父さん・お母さんの「最後のラブレター」であり、残される家族への「最強のお守り」です。
- Q2:親が認知症になってしまったら、もう手遅れですか?
-
これは非常に深刻な問題です。遺言書を書いたり、生前贈与をしたり、不動産を売却したりするには、ご本人の「意思能力(自分で判断できる力)」が必須です。
もし認知症が進行し、この意思能力がないと判断されると、法律上、一切の相続対策ができなくなります。
銀行口座は凍結され、不動産も売れなくなります。
これを解決するには「成年後見制度」という仕組みがありますが、手続きが非常に煩雑で、財産の自由度も下がってしまいます。だからこそ、「親が元気なうちに」話を進めることが、これほどまでに重要視されているのです。
- Q3:生命保険は、相続財産になるんですか?
-
素晴らしい質問です。これは専門家(保険代理店)としての大事なポイントです。
実は、生命保険の死亡保険金は、法律上(民法上)は「相続財産」ではありません。受取人として指定された人(例:妻)の「固有の財産」となります。
これが何を意味するかというと…
- 遺産分割協議(誰が何をどれだけもらうかの話し合い)の対象外。
- 遺留分(ポイント③)の計算対象からも、原則として外れる。
- 銀行が凍結されていても、受取人が請求すればスグに現金化できる。
つまり、「特定の誰かに、確実に、すぐに、現金を渡せる」という最強のツールなのです。
「介護で世話になった長男の嫁に、財産とは別に感謝の気持ちを渡したい」
「ウチは不動産ばかりだから、相続税を払うための現金を長男に用意しておきたい」
といったニーズに完璧に応えられます。
(※ただし、相続税の計算上(税法上)は「みなし相続財産」としてカウントされます。ここがややこしいのですが、「500万円 ×法定相続人の数」までは非課税枠があります。)
まとめ:後悔しない相続は「早めの相談」から
「相続の基本ルール5つのポイント」について解説してきましたが、いかがでしたか?
『なるほど、そういうことだったのか』と感じていただけたなら嬉しいです。
「法定相続人」「法定相続分」「遺留分」「基礎控除」「手続き期限」
この5つを知っているだけで、あなたの相続に対する不安は、かなり軽くなったのではないでしょうか。
ただし、相続は一つとして同じケースはありません。財産状況、家族構成、そして何より「家族の想い」が、すべてのご家庭で違うからです。
「うちの基礎控除はいくら?」
「この財産の分け方だと、揉めないかな?」
「親にどうやって切り出したらいいか、具体的に教えてほしい」
という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そんな時は、どうか一人で抱え込まず、遠慮なく無料相談をご活用ください。
私たち相続のプロフェッショナルが、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスをさせていただきます。
長年の経験から言えるのは、『早めの相談』が、後悔しない相続へのたった一つの、そして一番確実な第一歩だということです。
※ご相談は完全に無料です。保険の押し売りなどは一切いたしませんので、安心してお申し込みください。