相続放棄の判断基準【チェックリスト付】後悔しない選択のポイント
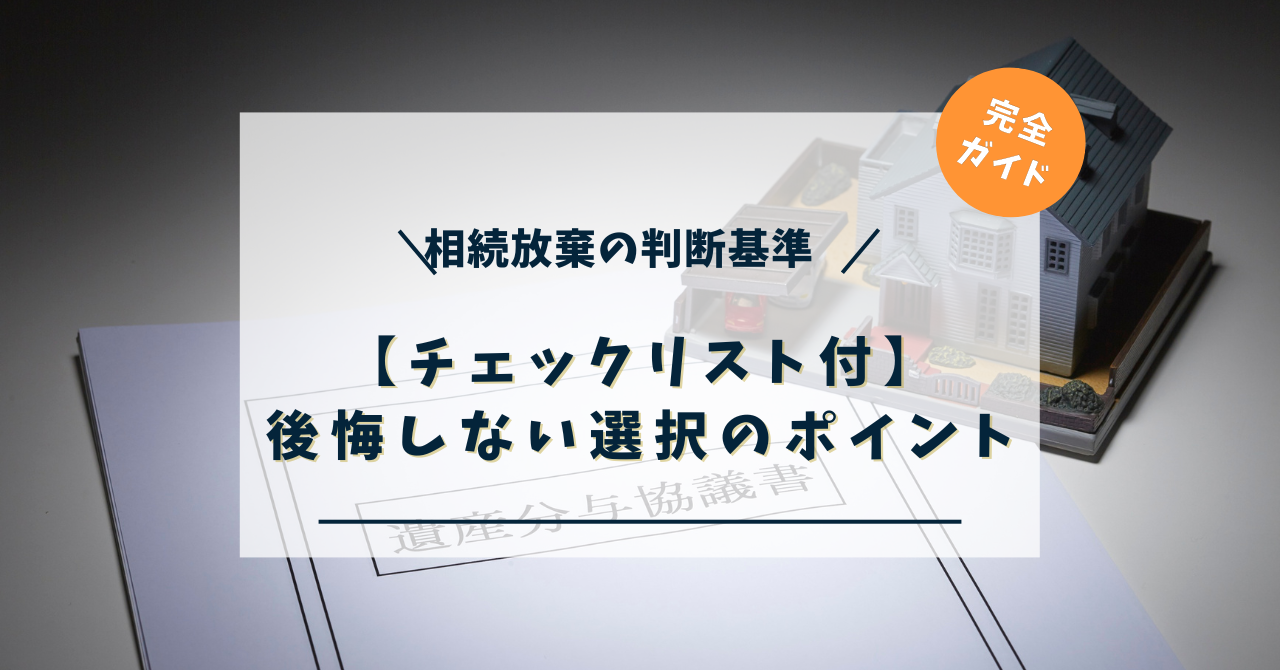
親しい方がお亡くなりになって色々な手続き中に
「どうやら借金があるらしい…」「故人が誰かの連帯保証人になっていたかも…」といった不安な情報が。
「相続放棄」という言葉が頭をよぎるものの、
「でも、もしプラスの財産が多かったらどうしよう?(損したくない)」
「放棄したら親不孝だと思われないか…親戚の目が怖い(感情)」
「期限が3ヶ月って短すぎる!仕事も家事もあるのに、調査なんて間に合うわけない!(焦り)」
と、不安と焦り、そして罪悪感が入り混じり、冷静な判断ができなくなっていませんか?
そのお気持ち、痛いほどわかります。相続放棄は、人生における重大な決断。しかも「一度選んだら、絶対に後戻りできない」というシビアなルール付きです。
特に「時間がない中で、何を優先して確認すべきか」という緊急度の視点と、「親戚付き合いへの不安」といった感情面も踏まえて、あなたが今すべきことを明確にします。
この記事を読み終える頃には、不安が整理され、「後悔しない選択」への第一歩を踏み出せるようになっています。まずは一緒に、状況を整理していきましょう。
1. 相続放棄の判断、その前に!知っておくべき「3つの選択肢」と「鉄の掟」
「借金があるかもしれないから、相続放棄しなきゃ!」
そう思い詰めていませんか?
もちろん、相続放棄は非常に強力で有効な手段です。しかし、焦って判断する前に、まずは深呼吸を。あなた(相続人)には、実は3つの選択肢が用意されています。そして、すべての選択肢に共通する「絶対に破ってはいけない鉄の掟」が存在するのです。
まずは全体像を把握して、冷静さを取り戻しましょう。
1-1. あなたの選択肢は「放棄」だけじゃない?
相続が開始された(故人が亡くなった)瞬間、あなたは自動的に「相続人」となります。その際、故人が残した財産(プラスの財産も、マイナスの財産も)をどう引き継ぐか、以下の3つから選ぶ権利があります。
- 単純承認(たんじゅんしょうにん)
- 限定承認(げんていしょうにん)
- 相続放棄(そうぞくほうき)
「え、単純になんとなく相続する以外に、そんな選択肢があったの?」と思われたかもしれません。
多くの人は、特に借金などがなければ、自然と「1. 単純承認」を選んでいます(正確には、何もしなければ自動的に単純承認になります)。
しかし、今回のように借金のリスクがある場合、「2. 限定承認」や「3. 相続放棄」が重要な選択肢として浮上してくるのです。
1-2. メリット・デメリット早見表:「単純承認」「限定承認」「相続放棄」
この3つ、一体何がどう違うのか。メリットとデメリットを表で比較してみましょう。
| 選択肢 | 内容 | メリット | デメリット |
| 1. 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて受け継ぐ。 | ・手続きが不要(何もしなければコレ)。 ・プラスの財産が多ければ当然オトク。 | ・借金が無限に降りかかる(無限責任)。 ・後から借金が見つかっても逃れられない。 |
| 2. 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を受け継ぐ。 | ・借金がいくらあっても、プラスの財産以上に返済しなくてよい(有限責任)。 ・もし財産が余れば、それをもらえる。 ・「実家だけは残したい」等の場合に有効なことも。 | ・手続きが非常に複雑で期限も3ヶ月。 ・相続人全員で申し立てが必要。 ・税金(みなし譲渡所得税)がかかる場合がある。 |
| 3. 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて手放す。 | ・借金や保証債務から完全に解放される。 ・手続きは比較的シンプル(自分でも可能)。 ・相続トラブルから離脱できる。 | ・一度行うと絶対に撤回(取り消し)できない。 ・実家や思い出の品など、プラスの財産も一切もらえない。 ・次の順位の相続人に権利が移る。 |
限定承認は、「プラスとマイナス、どっちが多いかわからない…」という時に最強に見える選択肢かもしれません。しかし、実務上は「相続人全員で」というハードルが非常に高く、手続きも煩雑なため、あまり利用されていないのが実情です。
多くの場合、現実的な選択は「単純承認(全部もらう)」か「相続放棄(全部捨てる)」かの二択になります。
1-3.【鉄の掟】相続放棄の期限は「知った時から3ヶ月」!
さて、ここが最重要ポイントです。
これらの選択肢(特に限定承認と相続放棄)を選ぶことができる期間は、法律で厳格に決まっています。
これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
「知った時」というのがミソで、例えば故人と疎遠にしており、死亡の事実を半年後に知らされた場合、その「知った日」から3ヶ月がスタートします。
とはいえ、ほとんどの場合は「亡くなった日」からカウントダウンが始まると考えておくべきです。
たった3ヶ月。この間に、「財産調査」をして、「判断」をし、「手続き(申述書の作成・提出)」まで完了させなければなりません。
これが、私たちが「焦ってください」とは言わないまでも、「スピードが命です」とお伝えする理由です。
1-4.【重要】絶対にやってはいけない「単純承認」とみなされる行為
「よし、3ヶ月あるなら、じっくり財産調査をしよう」
そう思ったあなた。ここで最大の落とし穴があります。
熟慮期間中(3ヶ月以内)であっても、あなたが故人の財産に手をつけてしまうと、その瞬間、あなたは「1. 単純承認(=全部相続します)」を選んだとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」と呼びます。
こうなると、後から借金が発覚しても、もう相続放棄はできません。
具体的には、以下のような行為です。
- 故人の預貯金を引き出して使う(※1)
- 故人の不動産や車を売却する、または自分の名義に変更する
- 故人の株式を売却する
- 故人の借金を(自分の財産から)返済する(※2)
- 高価な形見分けをする(例:「親父のロレックス、形見にもらっとこ」「お母さんの宝石、私がもらうわ」など)
(※1)葬儀費用に充てるための引き出しは、社会通念上の範囲内(領収書必須)であれば認められる傾向にありますが、非常にグレーゾーンです。できれば自分の財産で立て替え、相続財産には一切手を付けないのが賢明です。
(※2)故人の財産から返済するのはもちろんアウトです。よくあるのが、故人の財布に残っていた現金。
「あ、3万円入ってる。ラッキー。これで飲み代に…」
これをやった瞬間、数千万円の借金もセットで相続決定!なんていう、笑えないホラー話があり得るのです。
財産調査はしてもいい。しかし、処分・消費は絶対ダメ。これが、後悔しないための「鉄の掟」です。
2.【緊急度順チェックリスト】相続放棄すべきかの判断基準8選
3ヶ月というタイムリミットの中、冷静に判断するための「ものさし」が必要です。
ここでは、私たちが多くの相続現場で見てきた「相続放棄を選ぶべきか」の判断基準を、確認すべき緊急度の高い順に8つのチェックリスト形式でご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、一つずつ確認してみてください。
【緊急度:高】放置は危険!最優先で確認すべき基準
まずは「待ったなし」の項目です。これらに該当する場合、相続放棄の検討を最優先で行う必要があります。
2-1. [基準1] 故人は「連帯保証人」になっていなかったか?(最重要リスク!)
これが一番恐ろしいケースです。
通常の借金(例:消費者金融から100万円)であれば、マイナスは100万円で確定します。
しかし、「連帯保証人」の債務は、主債務者(お金を借りた本人)が払えなくなった瞬間に、全額が保証人に請求されます。それが数千万円、数億円であっても、です。
(例)
故人が知人の事業のために「5,000万円」の連帯保証人になっていた。
プラスの財産は「実家1,000万円」と「預金500万円」。
もし相続(単純承認)してしまうと、この「5,000万円の保証債務」も引き継ぎます。
相続後に知人が倒産した場合、あなたに5,000万円の返済義務が発生。プラスの財産1,500万円を差し引いても、残り3,500万円はあなた自身の財産から返済しなければなりません。
連帯保証債務は、故人の郵便物(金融機関や保証協会からの通知)や、金銭消費貸借契約書の控えなどで判明することが多いですが、見つかりにくいのが厄介な点です。少しでも可能性があるなら、調査を急ぎ、放棄の準備を進めるべきです。
2-2. [基準2] 明らかに借金が多い(債務超過)
これは最もわかりやすい基準です。
- プラスの財産: 預貯金、不動産(実家など)、有価証券(株など)、生命保険金(※これは厳密には相続財産ではありませんが、受け取れる財産として計算)など
- マイナスの財産: 借入金(住宅ローン、カードローン)、未払いの税金・健康保険料、未払いの家賃・医療費、連帯保証債務など
財産調査の結果、「プラスが500万円、マイナスが2,000万円」とはっきりわかれば、迷う必要はありません。
2-3. [基準3] 借金の全容が不明・3ヶ月で調査する時間がない
「どうも借金がありそうだけど、どこからいくら借りているのか、さっぱりわからない」
「故人とは疎遠で、財産状況なんて全く知らない」
このように、3ヶ月の熟慮期間内に負債の全体像が把握できそうにない場合も、安全策として相続放棄を選ぶ有力な理由になります。
相続放棄の撤回はできませんが、単純承認(相続する)の撤回もできません。
「よくわからないまま相続して、数年後に1,000万円の借用書がひょっこり出てきた…」というのが最悪のシナリオです。
わからない=リスクです。そのリスクを取れないのであれば、放棄が賢明な判断となります。
【緊急度:中】状況・希望別で判断すべき基準
次に、経済的な理由だけでなく、ご自身の状況や希望によって判断が分かれる基準です。
2-4. [基準4] 特定の相続人に財産(家業・実家)を集中させたい
「実家(家業)は長男にすべて継いでほしい」
「自分は遠方に住んでいるし、故郷の不動産をもらっても管理できない」
こんな時、相続放棄が使われることがあります。
例えば、相続人が子供3人(長男・次男・三男)で、長男に実家をすべて相続させたい場合。
通常の「遺産分割協議」で「私は財産をもらいません」という書面にサイン(実印)する方法もありますが、この方法だと故人の借金があった場合の返済義務は残ってしまいます(債権者に対抗できません)。
しかし、次男と三男が「相続放棄」をすれば、法的に「最初から相続人ではなかった」ことになります。
その結果、長男が唯一の相続人となり、プラスの財産(実家)もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐことになります。(※ただし、長男も借金が多ければ放棄を検討する必要があります)
2-5. [基準5] 面倒な相続トラブル・遺産分割協議から抜けたい
「相続人は自分と兄だが、兄とは昔から仲が悪く、絶対に揉める」
「他の相続人が多くて、話し合い(遺産分割協議)がまとまる気がしない」
故人に目立った借金がなくても、プラスの財産が少しでもあると、遺産分割協議は必要です。これが、いわゆる「争族」の入り口です。
「わずかなプラスの財産のために、精神をすり減らして骨肉の争いをするくらいなら、もう全部いらない。関わりたくない」
そう考える場合、相続放棄は法的にその輪から離脱できる有効な手段です。
2-6. [基準6] 疎遠だった・関わりたくない
「故人(例えば、離婚した実の親や、長年音信不通だった兄弟など)とは、何十年も会っていない」
「今さらその人の相続手続きに関わりたくないし、財産も借金も一切引き受けたくない」
このようなケースでも、相続放棄は有効です。
法的な親子・兄弟関係は戸籍上残っているため、何もしなければあなたは相続人です。相続放棄をすることで、その関係性から生じる相続上の義務と権利、すべてを断ち切ることができます。
【感情面】あなたの「心」は大丈夫?無視できない基準
最後は、お金や法律論だけでは片付けられない、あなたの「心」の問題です。これが判断を鈍らせる最大の要因になることもあります。
2-7. [基準7] 「親不孝」という罪悪感が判断を鈍らせていないか?
借金が多いのはわかっている。論理的に考えれば放棄すべき。
でも、「親が残したものを捨てるなんて、親不孝ではないか…」と、罪悪感で一歩が踏み出せない。
これは、とてもよくあるお悩みです。特に、故人との関係が良好だった方ほど、この葛藤に苦しみます。
ですが、考えてみてください。
もし、故人があなたの今の苦しみを知ったら、どう思うでしょうか?
「自分の借金のせいで、子供(あなた)の人生や、その先の孫の人生まで犠牲にしてほしい」
と願う親がいるでしょうか。
故人が残した借金を法的な手続きで整理し、あなたがあなたの人生をしっかり生きていくこと。それこそが、本当の意味での「親孝行」であり、故人が最も望むことではないでしょうか。
相続放棄は、逃げでも親不孝でもありません。残された家族を守るための、法律が認めた「誠実な選択」です。
2-8. [基準8] 親戚付き合い(次の相続人への影響)が心配
「自分が相続放棄したら、相続権が叔父さんや叔母さん(故人の兄弟)に移ってしまう」
「『面倒なものを押し付けやがって』と恨まれないか心配…」
これは非常に重要な視点です。
- 第1順位:子(子が放棄したら孫へ)
- 第2順位:親(子が全員放棄し、親が存命の場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子も親もいない、または全員放棄した場合)
もし、あなたが第1順位の子で、全員が相続放棄をすると、第2順位の親(故人の親=あなたの祖父母)に権利が移ります。祖父母も亡くなっているか放棄すると、第3順位である故人の兄弟姉妹(あなたの叔父・叔母)に相続権(と借金の督促)が移るのです。
だからこそ、相続放棄を決断する場合は、次の順位の相続人になる可能性のある方へ、事前に(あるいは放棄後速やかに)連絡を入れる配慮が、円満な親戚付き合いを続けるために非常に重要になります。
3.【時間がない人向け】判断を間違えない最低限の財産調査(3ヶ月の壁)
相続放棄すべきかの判断基準はわかりましたね。
しかし、その判断を下すためには、大前提として「プラスの財産」と「マイナスの財産」が、それぞれ“どれくらいあるのか”を把握しなければなりません。
「そんなこと言ったって、3ヶ月しかないじゃないか!」
その通りです。だからこそ、戦略が必要です。
3-1. 完璧は無理!「3ヶ月でここまでやればOK」な調査とは
まず、心構えとして非常に重要なことをお伝えします。
故人がきっちり財産目録を残してくれていない限り、100%の調査はプロでも困難です。
目指すべきは「100点の調査」ではなく、「相続放棄すべきかどうかの判断材料が揃う、70点の調査」です。
特に重要なのは「マイナスの財産」の調査です。
プラスの財産(資産)の取りこぼしは「損」で済みますが、マイナスの財産(負債)の見落としは、あなたの人生を「破綻」させかねません。
3-2. まずはコレだけ!マイナスの財産(借金・保証)の探し方
時間がありません。まずは以下の3点に絞って調査を開始してください。
① 郵便物・督促状のチェック
故人宛の郵便物は、宝の山(あるいは地雷の山)です。
最低でも過去1年分、可能なら故人の自宅にあるすべての郵便物をチェックします。
- 見るべきもの:
- 金融機関(銀行、信金、信組)からの通知
- 消費者金融、クレジットカード会社からの請求書、利用明細
- 税務署、役所からの納税通知書、督促状(未納の税金・保険料も負債です)
- 保証協会などからの通知(→連帯保証人の可能性アリ!)
「借金がありそう」と感じたら、絶対に「受取拒否」や「廃棄」をしてはいけません。現実を直視することが第一歩です。
② 通帳の引き落とし履歴のチェック
故人の預金通帳(最低過去3〜5年分)を確認し、不審な「出金」「引き落とし」がないかを確認します。
- 見るべきもの:
- 毎月決まった日に、決まった金額が引き落とされている(→ カードローンや借金の返済の可能性)
- 「〇〇クレジット」「〇〇ファイナンス」といった見慣れない会社名からの引き落とし
- 個人名義への定期的な振り込み(→ 個人的な借金の可能性)
③【必須】信用情報機関への開示請求
これがマイナス財産調査の「切り札」です。
故人がどこから借金(クレジットカードのキャッシングやローン含む)をしていたかは、「信用情報機関」に記録が残っています。
以下の3つの機関すべてに、相続人として「本人(故人)の信用情報」を開示請求してください。
- CIC(シーアイシー): 主にクレジット会社、信販会社系
- JICC(ジェイアイシーシー): 主に消費者金融系
- KSC(全国銀行個人信用情報センター): 主に銀行系
手続きは郵送が基本となり、戸籍謄本(故人の死亡と、あなたが相続人であることがわかるもの)などが必要で、開示まで1〜2週間かかります。
これは、今すぐ(できればこの記事を読んだ明日)にでも手続きを開始してください。
3-3. 次にコレ!プラスの財産(資産)の探し方
マイナスの調査と並行して、プラスの財産も探します。
① 不動産(実家など)
「確か実家があったはず」という場合は、その不動産の価値(時価)を把握する必要があります。
まずは市区町村の役所(資産税課など)で「名寄せ帳(なよせちょう)」を取得します。これは、その市区町村内で故人が所有していた不動産の一覧表です。
その上で、「固定資産税評価証明書」を取得し、だいたいの価値(※売却価格とは異なりますが、一つの目安になります)を把握します。
② 預貯金・有価証券(株など)
故人が利用していた銀行や証券会社がわかれば、窓口で「残高証明書」を発行してもらいます(要戸籍謄本など)。
どこの銀行を使っていたか不明な場合は、タンスや引き出しにあるキャッシュカード、通帳、あるいは郵便物からあたりをつけます。
③ 生命保険
「故人が生命保険に入っていたかも?」という場合、「生命保険契約照会制度」が利用できます。生命保険協会に照会をかけると、故人が加入していた保険契約の有無を(原則)すべての保険会社に調査してくれます。
ただし、生命保険金(死亡保険金)は、原則として相続財産ではなく「受取人固有の財産」です。そのため、あなたが受取人に指定されていれば、相続放棄をしても受け取れます。
3-4.【裏ワザ】どうしても間に合わない時の「期間伸長」の申請方法

「調査を始めたけど、3ヶ月じゃどう考えても終わりそうにない!」
ご安心ください。そんな時のために、法律は「裏ワザ」を用意しています。
それが「相続の承認又は放棄の期間の伸長(きかんしんちょう)」の申立てです。
これは、家庭裁判所に対して「財産調査が複雑で3ヶ月では判断できないので、期間を延長してください」とお願いする手続きです。
認められれば、さらに3ヶ月程度(裁判所の判断によります)の猶予がもらえます。
ただし、これは「3ヶ月の熟慮期間が過ぎる前」に申請しなければなりません。
「調査が間に合わなそう…」と感じたら、期限ギリギリではなく、期限の1〜2週間前までには家庭裁判所に相談・申立てを行うようにしましょう。
4. 相続放棄「後」に起きうること(デメリットと注意点)
財産調査の結果、「相続放棄」を決断したとします。
手続き(家庭裁判所への申述)が受理されれば、あなたは借金から解放されます。
しかし、その決断には「後戻りできない」重みと、あなた以外の人への「影響」が伴います。放棄した後で「知らなかった」と後悔しないよう、デメリットと注意点をしっかり押さえておきましょう。
4-1. 一度放棄したら「撤回」は絶対できない(最大の注意点)
これが相続放棄における最大の注意点です。
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたら、あとから「やっぱり相続する」と撤回(取り消し)することは、原則として絶対にできません。
「相続放棄した3ヶ月後に、故人がこっそり持っていた金(ゴールド)の延べ棒が1億円分、タンスの奥から出てきた!」
こんな、まるでドラマのような話があったとしても、「やっぱりあの放棄、ナシで!」とは言えないのです。
(※ただし、他の相続人から脅迫されて無理やり放棄させられた、など特殊な事情があれば取消しが認められる余地はありますが、極めて例外的です)
だからこそ、先ほど解説した財産調査が重要なのです。「プラスの財産が絶対にないか」をできる限り確認し、納得した上で決断する必要があります。
4-2. 相続権が「次の順位」の人に移る(兄弟姉妹・甥姪・叔父叔母への連絡は必須?)
2-8(判断基準)でも少し触れましたが、非常に重要な点なので詳しく解説します。
あなたが相続放棄をすると、法律上「あなたは最初から相続人ではなかった」とみなされます。
この「相続順位」は法律で決まっています。
- 第1順位: 子(子が全員放棄したら、孫へ)
- 第2順位: 直系尊属(故人の親。第1順位が全員放棄したら、こちらへ)
- 第3順位: 兄弟姉妹(第1・第2順位が全員放棄したら、こちらへ。兄弟姉妹が亡くなっていればその子=甥・姪へ)
(例)
故人Aさん(妻は先に死亡)。相続人は長男Bさん、長女Cさん。
故人の親(祖父母)は死亡。故人の兄弟(叔父・叔母)は存命。
借金が5,000万円あることがわかり、BさんとCさんが二人とも相続放棄。
↓
第1順位がいなくなったため、第2順位(故人の親)に権利が移るが、死亡しているためスルー。
↓
第3順位である故人の兄弟(叔父・叔母)が、新たな相続人となる。
もし、あなたがBさんやCさんの立場で、借金があることを知りながら、叔父・叔母に何の連絡もせずに自分たちだけ相続放棄したらどうなるでしょうか?
ある日突然、叔父・叔母のもとに、金融機関から「あなたが相続人になったので5,000万円返してください」という督促状が届くことになります。
当然、「なぜB(甥)は教えてくれなかったんだ!」と、親戚関係は修復不可能なレベルで悪化するでしょう。
相続放棄に、次の順位の相続人への「連絡義務」は法律上ありません。
しかし、道義的・感情的な配慮として、連絡は「必須」だと私たちは考えます。
「私たちが調査した限り、こういう理由(借金)で放棄することにした。申し訳ないが、そちらにも(相続放棄の)手続きが回ってしまうかもしれない」と一本電話を入れるだけで、未来のトラブルは大きく減らせます。
4-3. 実家(空き家)の管理責任が残るケースも?(2023年民法改正のポイント)
「借金も実家(空き家)も全部いらないから放棄した。これでスッキリ!」
…と、以前はそれで良かったのですが、2023年4月の民法改正(※)により、事情が少し変わりました。
(※正確には改正民法の施行)
【改正のポイント】
相続放棄をしても、その放棄によって「現に占有している」財産(多くの場合は実家)については、次の相続人や相続財産清算人(後述)が管理を始めることができるようになるまで、保存(管理)する義務を負う。
簡単に言えば、「相続放棄したから、あとは知らない」と実家を放置して、その結果、家が倒壊して隣家に損害を与えたり、放火されたりした場合、「管理責任を問われる可能性がある」ということです。
もし、あなたが相続放棄する財産の中に「空き家」が含まれており、他に管理する相続人がいない場合、最終的には家庭裁判所に「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)」の選任を申し立て、その清算人に財産(空き家)の管理を引き継いでもらうまで、責任が残る可能性があります。(※清算人の選任には費用(予納金)がかかります)
借金からは逃れられますが、空き家の管理責任からはすぐには逃れられないケースがある、と覚えておいてください。
4-4. 生命保険金や遺族年金は受け取れる?(放棄しても大丈夫なお金)
「相続放棄したら、故人がかけてくれていた生命保険ももらえないの?」
と心配される方が非常に多いですが、ご安心ください。
以下の2つは、そもそも「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。
- 生命保険金(死亡保険金)
- あなたが「受取人」として指定されている場合。
- 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)
- あなたが受給要件を満たしている場合。
これらは、あなたの生活を守るために国や保険会社から直接支払われるお金です。故人の借金とは切り離して考えられます。
ただし、故人自身が「受取人」になっていた保険金や、解約返戻金などは相続財産になるため、放棄すると受け取れませんのでご注意ください。
5. 相続放棄の手続きの流れと費用(自分でやる?専門家に頼む?)
相続放棄をすると決断したら、次はいよいよ「手続き」です。
「裁判所の手続き」と聞くと、なんだか難しそうで尻込みしてしまうかもしれません。
ですが、相続放棄の手続き(申述)自体は、ポイントさえ押さえれば自分で行うことも可能です。
ここでは、手続きの流れ、かかる費用、そして「自分でやるべきか、専門家に頼むべきか」の判断基準を解説します。
5-1. 申述書の提出先(家庭裁判所)と必要書類
相続放棄は、市役所や法務局に書類を出すのではありません。
「故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てる必要があります。
【主な必要書類】
手続きには、以下の書類(とコピー)が必要です。
- 相続放棄の申述書(しんじゅつしょ)
- 裁判所の窓口やウェブサイトで取得できます。
- 「放棄の理由」などを記載します。
- 故人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 故人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
- 申述人(あなた)の戸籍謄本
※注意点
あなたが故人とどういう関係(子か、兄弟か、孫かなど)によって、必要な戸籍謄本の範囲(故人の出生から死亡まで全て、など)が異なります。必ず事前に管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
これらの書類を揃えて家庭裁判所に提出(郵送可)し、不備がなければ、後日「相続放棄申述受理通知書」という書類が自宅に届きます。この通知書が、あなたが相続放棄したことの公的な証明書となります。
5-2. 自分でやる場合の費用 vs 専門家(司法書士・弁護士)に依頼する費用相場
手続きにかかる費用は、大きく「実費」と「専門家報酬」に分かれます。
① 自分でやる場合
自分で手続きする場合にかかるのは「実費」のみです。
- 収入印紙代:800円(申述人1人あたり)
- 連絡用の郵便切手代:数百円程度(裁判所によります)
- 戸籍謄本などの取得費用:数千円程度
- 合計:約3,000円~10,000円程度
このように、実費自体は非常に安価です。
② 専門家に依頼する場合
「忙しくて書類を集めたり作ったりする時間がない」「戸籍の収集が複雑でわからない」という場合は、専門家に依頼します。
- 司法書士に依頼する場合
- 報酬相場:1人あたり 3万円~7万円程度(+実費)
- 主に書類の作成・収集・提出代行がメインです。相続放棄の手続きだけをスムーズに行いたい場合に適しています。
- 弁護士に依頼する場合
- 報酬相場:1人あたり 5万円~10万円程度(+実費)
- 書類作成代行に加え、債権者(借金の取立先)との交渉窓口になったり、3ヶ月の期間伸長を代理で行ったり、他の相続人と揉めている場合の交渉など、より広範な対応が可能です。
5-3. 専門家に頼むべきケースとは?
「安いなら自分でやりたいけど、自分の場合はどうだろう?」と迷いますよね。
以下のようなケースに当てはまる場合は、費用がかかっても専門家(司法書士または弁護士)に依頼することを強くお勧めします。
- 相続開始(死亡)から3ヶ月の期限が迫っている
- 自分で戸籍を集めたり書類の書き方を調べているうちに、期限が過ぎてしまうリスクがあります。スピードが最優先です。
- 自分で戸籍を集めたり書類の書き方を調べているうちに、期限が過ぎてしまうリスクがあります。スピードが最優先です。
- 財産調査が複雑で、期間伸長(3-4参照)も検討している
- 期間伸長の申立ても含めて、プロに任せた方が確実です。
- 期間伸長の申立ても含めて、プロに任せた方が確実です。
- すでに債権者から督促状が届いており、精神的にキツい
- 弁護士に依頼すれば、債権者への対応窓口になってもらえます。「〇〇弁護士に依頼しました」と伝えるだけで、あなたへの直接の督促が止まる(ことが多い)のは大きな精神的メリットです。
- 弁護士に依頼すれば、債権者への対応窓口になってもらえます。「〇〇弁護士に依頼しました」と伝えるだけで、あなたへの直接の督促が止まる(ことが多い)のは大きな精神的メリットです。
- 他の相続人(特に次の順位の親戚)との関係が複雑で、連絡調整に不安がある
- 故人と疎遠で、戸籍の収集が困難(どこまで遡ればいいかわからない)
相続放棄は「失敗が許されない」手続きです。
数万円の費用を節約しようとして、期限(3ヶ月)を徒過し、数千万円の借金を背負ってしまっては、元も子もありません。
「少しでも不安がある」「時間がない」と感じたら、まずは無料相談などを利用して専門家にアクセスすることをお勧めします。
6. よくある質問(FAQ)
相続放棄に関して、多くの方が抱える疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。
Q1. 相続放棄をしたら、親戚に連絡すべきですか?どう伝えれば角が立ちませんか?
法的な連絡義務はありませんが、後のトラブルを避けるためにも連絡は強く推奨します。「調査の結果、プラスの財産を大きく超える借金(または連帯保証)が判明し、私たち家族を守るために苦渋の決断として放棄した」という事実と経緯を誠実に伝えましょう。「ご迷惑をおかけして申し訳ないが、そちらにも相続権が移るため、ご自身でも放棄の手続きをご検討ください」と、情報提供と謝罪の形で伝えるのが角を立てないコツです。
Q2. 借金がいくらかわからないまま3ヶ月が過ぎそうです…どうすれば?
絶対に放置してはいけません。期限が過ぎる前に、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長(期間伸長)」を必ず申し立ててください。「故人と疎遠で財産調査に時間がかかっている」など正当な理由があれば、裁判所は熟慮期間を延長してくれます。3ヶ月を1日でも過ぎると(原則として)単純承認とみなされ、手遅れになります。
Q3. 故人の預金を葬儀代として少し使ってしまったら、もう相続放棄できませんか?
非常に危険なグレーゾーンです。「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が認められない可能性が高くなります。判例では、故人の財産から支出しても社会通念上相当な範囲(豪華すぎない葬儀費用など)であればセーフとされることもありますが、リスクが大きすぎます。葬儀費用はご自身の財産で立て替え、故人の財産には一切手を付けないのが鉄則です。
Q4. 父が亡くなり相続放棄した後、祖父が亡くなった場合、祖父の財産は代襲相続できますか?
はい、代襲相続できます。相続放棄の効果は、その放棄した「父の相続」に関してのみ及びます。あなたが父の相続を放棄したからといって、父とあなたの親子関係が消滅するわけではありません。したがって、その後に祖父が亡くなった場合、あなたは「祖父の相続人(本来相続するはずだった父の代わり=代襲相続人)」として、祖父の財産を相続する権利を持ちます。
Q5. 専門家に相談するベストなタイミングはいつですか?
「相続放棄したほうがいいかも?」と少しでも迷った瞬間がベストタイミングです。特に「故人に借金がありそう」「3ヶ月の期限管理に自信がない」「相続人が多い、または疎遠な親戚がいる」のどれか一つでも当てはまるなら、財産調査と並行してでも、すぐに司法書士や弁護士の無料相談を利用すべきです。手遅れになる前の「転ばぬ先の杖」として専門家を活用してください。
7. まとめ:相続放棄は「情報収集」と「スピード」が命。後悔のない選択を。
最後に、後悔しない選択のために絶対に押さえておくべき5つの重要ポイントをまとめます。
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3択があります。判断期限は「知った時から3ヶ月」。この期間(熟慮期間)が勝負の分かれ目です。
通常の借金より恐ろしいのが「連帯保証債務」です。故人が保証人になっていないか、信用情報機関(CIC/JICC)の照会などで最優先で確認しましょう。
預金の引き出しや形見分けなど、財産を処分・消費すると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなります。葬儀費用も立て替えるのが安全です。
相続放棄は一度きり。絶対に撤回できません。また、相続権は次の順位(兄弟姉妹や叔父叔母など)に移るため、トラブル防止の事前連絡は必須です。
3ヶ月で判断できなければ「期間伸長」を申請。少しでも不安なら、費用を惜しまず司法書士や弁護士に相談を。期限徒過が最大のリスクです。