【完全ガイド】相続手続きの流れ→期限・必要書類・費用を一覧化
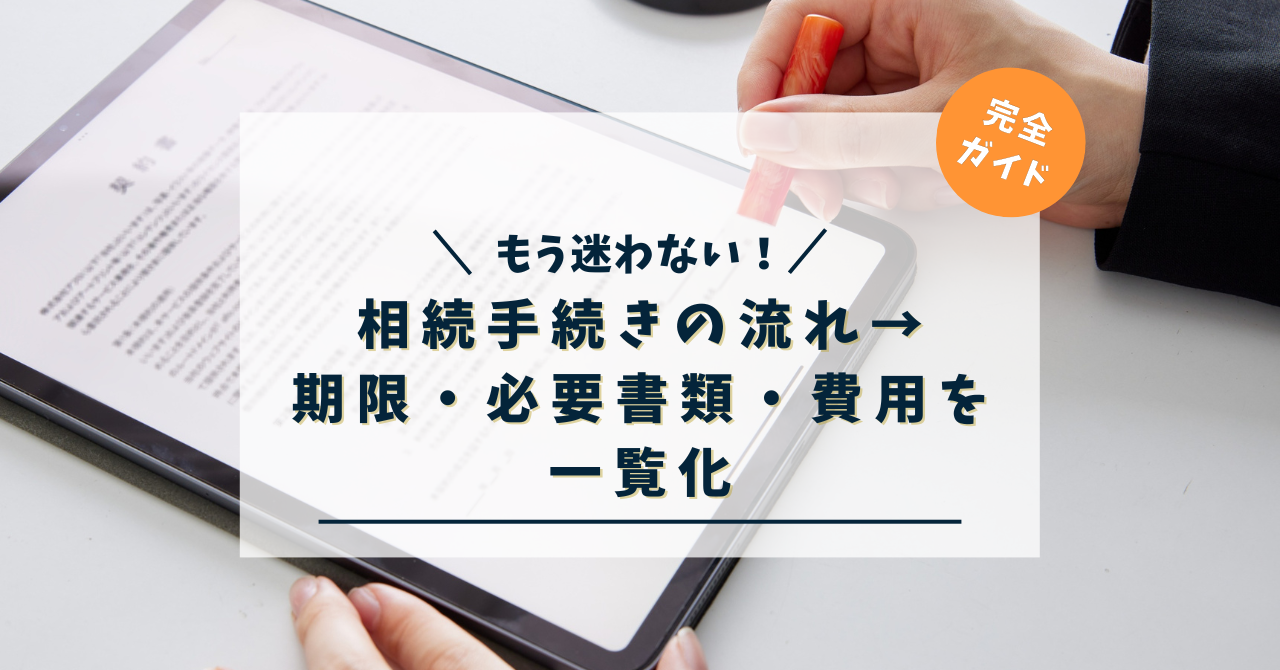
もし、ご家族に万が一のことがあったら…。
その時、何から手をつければいいのか、具体的にイメージできますか?
- 「相続手続きって、すごく大変そう…」
- 「死亡届? 相続放棄? 期限が色々あるって聞くけど、順番がわからない」
- 「親も高齢になってきたし、いざという時の流れを知っておきたい」
- 「うちは財産も少ないと思うけど、何かしなきゃいけないの?」
こうした漠然とした不安を抱えながらも、「まだ先のこと」とつい後回しにしてしまいがちですよね。
ですが、そのお気持ち、よくわかります。
相続手続きは、いざその時が来ると、悲しむ間もなく期限に追われるのが現実。だからこそ、「いつか」のために「今」、全体の流れを知っておくことが何よりの「お守り」になるんです。
相続手続きは、「①全体像の把握」と「②最重要の5大期限」さえ事前に押さえておけば、いざという時に慌てず、冷静に対応できます。
この記事では、「その時」が来たら何をすべきか、「相続手続きの全流れ」「期限」「必要書類」「費用」を、日本一わかりやすく、時系列の【完全ガイド】としてまとめました。
漠然とした不安を、「知っている」という安心感に変えるところから、スタートです。
【まず落ち着いて】ご家族に万が一のことがあったら…まずやるべきこと
あなたの不安は「全体像がわからない」ことから来ています
結論から申し上げます。今あなたが感じている「相続って大変そう」という漠然とした不安の正体は、「次に何をすべきか、全体像がわからない」という未知への不安です。
なぜなら、人の脳は「何を」「いつまでに」「いくつやれば」終わりなのかが明確になれば、驚くほど冷静さを取り戻せるからです。
いざご家族が亡くなられた直後は、誰もが冷静ではいられません。そんな中で「相続」という言葉が飛び交うと、まるでラスボスがいきなり目の前に現れたような気分になりますよね。
しかし、安心してください。相続手続きは、確かに複雑で多岐にわたりますが、決して「攻略不可能なダンジョン」ではありません。
大丈夫。相続手続きは「期限」と「順番」だけ押さえれば怖くない
相続手続きを乗り切るコツは、たった2つ。「守るべき期限」と「進めるべき順番」を把握することです。
相続手続きの多くは、「死亡届は7日以内」「相続放棄は3ヶ月以内」といったように、法律で明確な期限が決められています。この期限を守りさえすれば、取り返しのつかない事態は防げます。
そして、手続きには「まず戸籍を集めて相続人を確定させる」→「次に財産を調べる」→「そして皆で分ける」という、攻略すべき「順番(流れ)」があります。
この「期限」と「順番」さえ間違えなければ、あとは一つずつ着実にクリアしていくだけなのです。
【最優先】まず7日以内に行う手続き(死亡届・葬儀)
とはいえ、理屈はわかっても「じゃあ、いざという時、まず何をするの?」というのが一番知りたいことですよね。
- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り
- 通常、臨終に立ち会った医師(または警察の監察医)が作成してくれます。これがなければ何も始まりません。役所への提出や保険金請求などでコピーが必要になることが多いので、いざという時は、原本を提出する前に必ず10枚ほどコピーを取っておくと覚えておきましょう。あのコンビニのコピー機で、人生で一番真剣にコピーを取る瞬間が来るかもしれません。
- 死亡届の提出(7日以内)
- 死亡診断書と一体になっている「死亡届」に必要事項を記入し、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に提出します。
- 多くの場合、葬儀社が手続きを代行してくれますので、まずは葬儀社に相談するのが一番スムーズです。
- 火葬(埋葬)許可証の取得と葬儀の手配
- 死亡届を提出すると、引き換えに「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。これが無いと火葬ができません。これも葬儀社が一緒に手配してくれます。
まずは、葬儀社としっかり連携を取り、この「7日以内の手続き」を乗り切ることに集中する必要があります。年金や健康保険の手続き(14日以内)も続きますが、まずはこの最初の7日間が第一関門です。
この記事が「相続手続きの攻略本」になります(約束すること)
この記事では、最初の7日間を乗り越えた後、あなたを待ち受ける「相続手続きの全流れ」を、期限順にわかりやすく解説していきます。
- 命運を分ける「5大期限」は何か?
- 結局、全部で何ステップあるのか?
- どんな書類が必要で、どこで取るのか?
- 費用はいくらかかるのか?
読み終える頃には、あなたの不安は「何をすべきかわかった」という安心感に変わっているはずです。一緒に一つずつ進めていきましょう。
1. 【最重要】相続手続き、命運を分ける「5大期限」
相続手続きは「10ヶ月」が一区切り。でも重要な関所は5つ
結論から申し上げます。相続手続きの全体像は約10ヶ月が一区切りとなりますが、その道中には絶対に通過しなければならない「5つの重要な関所(期限)」があります
なぜなら、これらの期限を1日でも過ぎてしまうと、「借金を強制的に相続してしまう」「税金で大きな損をする」「罰則(過料)の対象となる」といった、取り返しのつかないデメリットが生じる可能性があるからです。
「親が亡くなって悲しいのに、期限なんて…」と思われるかもしれませんが、法律は待ってくれません。この5つの期限だけは、カレンダーに赤丸をつけておく意識でご確認ください。
① 7日以内:死亡届の提出
- 期限:死亡の事実を知った日から7日以内
- 内容:故人が亡くなったことを法的に届け出る手続きです。
- なぜ重要か?:
最初でも触れましたが、これが全ての始まりです。この届出をしないと「火葬(埋葬)許可証」が発行されず、葬儀を進めることができません。とはいえ、ここは葬儀社がほぼ100%代行してくれるので、ご遺族が直接役所に走るケースは稀です。「葬儀社に死亡診断書を渡す=死亡届の手続き」と覚えておけば大丈夫です。
② 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の判断(全財産の調査完了)
- 期限:相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内
- 内容:相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切相続しない「相続放棄」、またはプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する「限定承認」を家庭裁判所に申し立てる期限です。
- なぜ重要か?:
これが第一の「命運の分かれ道」です。 もし、故人に多額の借金があった場合、この3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをしないと、原則として全ての借金を引き継ぐことになってしまいます(これを「単純承認」と呼びます)。
「え、うちの親に限って借金なんて…」と思っていても、連帯保証人になっているケースもあります。この3ヶ月以内に「財産調査(借金がないかどうかの調査)」を終え、「相続するか、しないか」を決断する必要があるのです。
③ 4ヶ月以内:準確定申告(故人の所得税)
- 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
- 内容:故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得に対する「所得税の確定申告」です。
- なぜ重要か?:
故人が生前に事業(自営業)をしていた、家賃収入があった、または年金以外の収入(例:株の売却益など)が多かった場合、この申告が必要です。逆に、故人が会社員や公的年金のみの受給者だった場合は、不要なケースが多いです。
もし申告が必要なのに忘れると、無申告加算税や延滞税といった余計な税金(ペナルティ)がかかってしまいます。
④ 10ヶ月以内:相続税の申告・納付
- 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
- 内容:相続した財産の総額が「基礎控除額」を超える場合に、相続税を計算して税務署に申告し、納税する期限です。
- なぜ重要か?:
これが第二の「命運の分かれ道」です。 まず、相続税は(後述しますが)9割のご家庭ではかかりません。しかし、もし基礎控除額を超える場合は、この10ヶ月以内に申告・納付を済ませないと、税金を大幅に優遇してくれる特例(例:配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)が使えなくなってしまいます。
特例が使えないと、相続税額が何倍にも跳ね上がることも…。さらに、延滞税などのペナルティも発生します。この10ヶ月が、相続手続きの「最大の山場」と言われる理由です。
⑤ 3年以内:相続登記(不動産の名義変更)【2024年義務化】
- 期限:相続(または遺産分割)で不動産の取得を知った日から3年以内
- 内容:故人名義の不動産(実家、土地など)を、相続した人の名義に変更する手続き(相続登記)です。
- なぜ重要か?:
これが今、最も注目されている「新しい関所」です。 以前は相続登記に期限はありませんでしたが、空き家問題の対策として、2024年4月1日から義務化されました。
正当な理由なくこの3年以内の登記を怠ると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。10ヶ月を過ぎても、この「3年ルール」があることを絶対に忘れないでください。
【全体像】相続手続きの流れを「5ステップ」で徹底解説
前の章で「5大期限」を確認しましたので、ここではそれらの期限を含め、相続手続きの開始から完了までの具体的な流れ(順番)を「5つのステップ」に分けて解説します。
「今、自分はどの段階にいるのか?」を把握するためのロードマップとしてご活用ください。
相続手続きのタイムライン(流れと期限の目安)
まずは全体像として、各ステップと期限の目安、主な「やること」を表にまとめます。
| ステップ | 期限の目安 | 主な「やること」 | 関連する5大期限 |
| ステップ1 | 死亡後~14日 | 死亡届の提出、葬儀の手配、役所への諸届(年金停止、健康保険証返却など) | ① 7日以内 |
| ステップ2 | ~3ヶ月以内 | 【最重要】 ・遺言書の有無を確認 ・相続人を確定(戸籍収集) ・相続財産を調査(借金含む) ・相続放棄/限定承認の判断 | ② 3ヶ月以内 |
| ステップ3 | ~4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得税申告) | ③ 4ヶ月以内 |
| ステップ4 | ~10ヶ月以内 | ・遺産分割協議(相続人全員で話し合い) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告・納付(必要な場合) | ④ 10ヶ月以内 |
| ステップ5 | 10ヶ月以降~ | ・各種名義変更(預貯金、株式、車など) ・不動産の名義変更(相続登記) | ⑤ 3年以内 |
ステップ1:死亡直後の手続き(~14日)
【このステップでやること】
それが落ち着くと、今度は「14日以内」に済ませるべき役所手続きが待っています。
- 年金受給権者死亡届(10日または14日以内)
- 健康保険証の返却、葬祭費・埋葬料の請求(期限は様々)
- 世帯主の変更届(14日以内)
- 公共料金や携帯電話などの名義変更・解約
これらは細々としていますが、忘れると故人宛の請求が続いたり、もらえるはずのお金(葬祭費など)がもらえなくなったりします。一つずつチェックリストにして潰していくのが確実です。
ステップ2:相続の「調査」と「判断」(~3ヶ月以内)
【このステップでやること】
この3ヶ月間は、「相続するか、しないか」を判断するための「調査期間」と心得てください。
- 遺言書の有無を確認する
- まず、故人が遺言書(特に公正証書遺言)を残していないか探します。もし法務局(または公証役場)以外で見つかった場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
- まず、故人が遺言書(特に公正証書遺言)を残していないか探します。もし法務局(または公証役場)以外で見つかった場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
- 相続人を確定させる(戸籍収集)
- 誰が相続人なのかを法的に確定させるため、故人の「出生から死亡まで」の全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めます。これが相続手続きで一番「面倒くさい」と言われる作業です。
- 誰が相続人なのかを法的に確定させるため、故人の「出生から死亡まで」の全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めます。これが相続手続きで一番「面倒くさい」と言われる作業です。
- 相続財産を調査する(財産目録の作成)
- 預金通帳、不動産の権利証、証券会社の取引残高報告書、生命保険証券などをかき集めます。
- 同時に、借金やローンの契約書、督促状、連帯保証人になっていないかなども徹底的に調べます。
- 相続放棄・限定承認の判断
- 調査の結果、「明らかに借金の方が多い」と判明したら、3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをします。
ステップ3:準確定申告(~4ヶ月以内)
【このステップでやること】
故人が「確定申告が必要な人」だった場合、相続人が代わって申告と納税を行います。
- 必要な人(例):自営業者、不動産(家賃)収入があった人、年金以外に多額の収入があった人
- 不要な人(例):給与所得のみの会社員(年末調整済み)、公的年金のみで生活していた人
「うちは関係ないかも」と思っても、念のため故人の収入状況は確認しておきましょう。
ステップ4:遺産分割と相続税申告(~10ヶ月以内)
【このステップでやること】
このステップは「どう分けるか」と「税金を払うか」の2段階です。
- 遺産分割協議
- ステップ2で確定させた相続人全員で、「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかを話し合います。電話やメールでも構いませんが、全員の合意が必須です。ここで揉めてしまうと、10ヶ月の期限に間に合わなくなる恐れがあります…。
- ステップ2で確定させた相続人全員で、「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかを話し合います。電話やメールでも構いませんが、全員の合意が必須です。ここで揉めてしまうと、10ヶ月の期限に間に合わなくなる恐れがあります…。
- 遺産分割協議書の作成
- 全員の合意が取れたら、その内容を書面にし、全員が実印を押して印鑑証明書を添付します。これが後の名義変更(ステップ5)で必須の書類となります。
- 全員の合意が取れたら、その内容を書面にし、全員が実印を押して印鑑証明書を添付します。これが後の名義変更(ステップ5)で必須の書類となります。
- 相続税の申告・納付
- 【FPコラム】で後述しますが、財産総額が「基礎控除」を超える場合のみ、税理士に依頼するなどして相続税を計算し、税務署に申告・納付します。
ステップ5:各種名義変更(10ヶ月以降~)
【このステップでやること】
遺産分割協議書(または遺言書)に基づき、各財産の名義を変更していきます。
- 預貯金の解約・名義変更(金融機関)
- 株式、投資信託の名義変更(証券会社)
- 生命保険金の請求(保険会社)
- 自動車の名義変更(運輸支局)
- 不動産の名義変更=相続登記(法務局)
特に最後の「相続登記」は、見出し1で触れた通り、2024年4月から3年以内の手続きが義務化されました。10ヶ月が過ぎても「忘れてた!」とならないよう、速やかに済ませてしまいましょう。
【FPコラム】相続税、うちも払う?「基礎控除」で9割の人は申告不要です
相続手続きと聞くと、「相続税って高いんでしょ?」と心配される方が非常に多いです。
しかし、ご安心ください。
結論から言うと、相続税の申告が必要なご家庭は、全体の約9%(令和4年データ)しかありません。
なぜなら、相続税には「基礎控除」という非常に大きな非課税枠があるからです。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が「配偶者と子2人」(合計3人)の場合、
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
となり、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税は1円もかかりませんし、税務署への申告も不要です。
ただし、ここで絶対に注意してほしいことがあります。
「相続税の申告が不要」=「相続手続きが不要」では、決してありません!
- 相続税が0円でも、遺産分割協議(ステップ4)は必要です。
- 相続税が0円でも、預貯金の解約(ステップ5)は必要です。
- 相続税が0円でも、不動産の相続登記(ステップ5)は義務です。
この違いを理解しておくことが、相続手続きのゴールを見誤らないために非常に重要です。
【全網羅】相続手続きの必要書類チェックリスト
相続手続きを進める上で、誰もが一度は「なぜこんなに書類が必要なんだ…」と壁にぶつかります。特に「戸籍謄本」の収集は、相続手続きの最初の関門とも言えます。
この章では、「どの手続きに」「どんな書類が必要か」を一覧表でチェックできるようにまとめました。
なぜ「戸籍謄本」が大量に必要なのか?
例えば、銀行や法務局(登記所)は、故人の預金や不動産を相続人に払い出す(名義変更する)責任があります。もし、後から「私にも相続する権利があった!」という人(例えば、故人が過去に認知していた子など)が現れたら、大トラブルになりますよね。
そうした事態を防ぐため、金融機関や法務局は、「故人の出生から死亡まで」の連続した全ての戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を見て、法定相続人が何人いるのかを厳密に確定させる必要があるのです。
故人が結婚や転籍で本籍地を何度も変えている場合、その全ての役所から戸籍を取り寄せる必要があり、これが「面倒くさい」と言われる正体です。
(表)手続き別:必要書類と取得場所一覧
ここでは、ステップ2以降の主な手続きで必要となる書類を一覧にしました。
(※あくまで一般例です。金融機関や事案によって異なる場合があります。)
| 手続きの段階 | 主な必要書類 | 取得場所(例) |
| ステップ1 (死亡届・年金等) | ・死亡診断書(死体検案書) ・死亡届(届出人の印鑑) ・年金手帳、健康保険証(返却用) | 病院 市区町村役場 自宅(故人) |
| ステップ2 (相続人・財産調査) | 【相続人確定のため】 ・被相続人(故人)の出生~死亡までの戸籍謄本一式 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 【財産調査のため】 ・預金通帳、残高証明書 ・証券会社の取引残高報告書 ・生命保険証券 ・固定資産評価証明書(または納税通知書) | 故人・相続人の各本籍地 相続人の各本籍地 金融機関 証券会社 保険会社 市区町村役場(都税事務所) |
| ステップ4 (遺産分割協議) | ・上記(ステップ2)で集めた書類一式 ・財産目録(調査結果をまとめたもの) ・相続人全員の印鑑証明書(発行3ヶ月または6ヶ月以内) ・遺産分割協議書(全員の実印で押印) | 相続人の各市区町村役場 (相続人で作成) |
| ステップ5 (相続登記・預貯金解約) | ・上記(ステップ4)で完成した書類一式 ・(相続登記の場合)登記申請書 ・(金融機関の場合)各社所定の払戻請求書 | 法務局 各金融機関 |
【書類のポイント】
- 固定資産評価証明書:これは不動産(土地・家屋)の公的な価値を示す書類です。相続登記の際の登録免許税(税金)の計算や、遺産分割で「不動産の価値はいくらとするか」を決める基準、相続税申告の際の評価額として使われる、非常に重要な書類です。
- 印鑑証明書:遺産分割協議書に押す実印が「本人のもの」であることを証明するために必須です。金融機関の手続きなどでも多用します。
FPが教える「戸籍集め」を効率化する裏ワザ(広域交付制度)
この面倒な戸籍集めですが、朗報があります。
2024年3月1日から「戸籍の広域交付制度」がスタートしました
これにより、故人の本籍地が全国各地に点在していても、最寄りの市区町村役場の窓口で、まとめて取得できる(請求できる)ようになりました。
これまでは、故人の本籍地が「新潟県→東京都→大阪府」と移っていた場合、それぞれの役所に個別に郵便請求などをする必要がありました。これが大幅に簡略化されたのです。まるでゲームの「ファストトラベル」が解禁されたようなものです。
ただし、いくつか注意点があります。
- 請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)のみです。(※専門家(司法書士など)による職務上請求は、現時点(2025年11月)でこの広域交付の対象外となるケースが多く、従来の取得方法となる場合があります)
- コンピュータ化されていない古い戸籍(手書き)などは対象外となる場合があります。
- 請求する人の本人確認(顔写真付き身分証明書)が厳格に求められます。
とはいえ、相続人ご自身で集める場合、この制度を使わない手はありません。役所の窓口で「広域交付で、父の出生から死亡までの戸籍をください」と相談してみましょう。
【相場一覧】相続手続きにかかる「実費」と「専門家報酬」
相続手続きを進める上でかかる費用は、大きく分けて「①必ずかかる実費」と、専門家に依頼した場合にかかる「②専門家への報酬」の2種類があります。
「うちは財産がないから…」という方でも、①の実費は(少額とはいえ)必ず発生します。まずはこの2つの違いをハッキリさせましょう。
① 必ずかかる「実費」はいくら?
実費とは、役所や法務局、金融機関などに支払う「手数料」や「税金」のことです。誰がやっても必ずかかる費用ですね。
- 1. 書類取得費用
- H3で解説した戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍(1通750円)、印鑑証明書(1通300円程度)、固定資産評価証明書(1通300円程度)などです。
- 相続人の数や故人の本籍地の移動回数によりますが、全部で数千円~1万5,000円程度になるのが一般的です。
- 2. 登録免許税(不動産登記)
- これが実費の中で最も大きくなる費用です。
- 故人名義の不動産(実家など)を相続人名義に変更(相続登記)する際に、法務局へ納める税金です。
- 税額は「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」と決まっています。
- (例)評価額が2,000万円の実家なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円 の登録免許税がかかります。
- 3. その他
- 預金通帳の残高証明書の発行手数料(1通1,000円前後)、家庭裁判所への申述費用(相続放棄など)、郵便代(郵送でやり取りする場合)など、細かな費用も発生します。
② 専門家に頼むといくら?(手続き別・費用概算表)
こちらは、2章や3章で解説したような「面倒な手続き」を、相続のプロ(司法書士・税理士・行政書士など)に代行してもらうための「手間賃(報酬)」です。
「どこまで自分でやって、どこからプロに任せるか」で総額は大きく変わります。以下に、一般的な手続きごとの費用相場(報酬)をまとめました。
【相続手続きの費用概算表(専門家報酬の目安)】
| 依頼内容 | 依頼する専門家(例) | 費用相場(報酬のみ) | 備考(別途実費がかかります) |
| 戸籍収集・相続人調査 | 司法書士・行政書士 | 3万円 ~ 10万円 | 戸籍の通数や相続関係の複雑さによる |
| 財産調査・財産目録作成 | 司法書士・税理士・銀行 | 5万円 ~ 20万円 | 調査する財産の種類や量による |
| 遺産分割協議書作成 | 司法書士・行政書士 | 5万円 ~ 15万円 | 相続人の数や財産内容による |
| 相続登記(不動産名義変更) | 司法書士 | 7万円 ~ 15万円 | 不動産の数や評価額による(※登録免許税は別) |
| 相続放棄の申述サポート | 司法書士・弁護士 | 3万円 ~ 7万円(1人あたり) | 裁判所への申立書類作成 |
| 相続税申告 | 税理士 | 遺産総額の0.5%~1.0% | 最低報酬20万円~が一般的。財産評価の難易度による |
| 相続手続き一式代行 (戸籍~預金解約・登記まで) | 司法書士・銀行(信託銀行) | 30万円 ~ 100万円以上 | 「遺産整理パック」など。財産額や内容で変動 |
【費用のポイント】
- 司法書士:主に「相続登記」や「戸籍収集」「遺産分割協議書作成」など、法務局や裁判所関係の書類作成のプロです。相続手続きの「入り口から名義変更まで」を幅広くカバーできます。
- 税理士:唯一「相続税申告」を代行できるプロです。相続税がかかるご家庭は、必須のパートナーとなります。
- 行政書士:「遺産分割協議書作成」や「自動車の名義変更」などを扱えますが、「相続登記」はできません。
- 弁護士:唯一「相続トラブル(揉め事)」の交渉代理人になれるプロです。費用は上記より高額になる傾向がありますが、揉めている場合は弁護士一択です。
どの専門家に頼むかは、あなたが「何に一番困っているか(面倒くさいか)」で決まります。
「うちは相続税はかからないけど、不動産(実家)があるし、戸籍集めも面倒…」という場合は、司法書士が最もコストパフォーマンス良く対応できるケースが多いですね。
相続手続きは自分でできる?専門家に依頼すべき?【FPの判断基準】
前の章で専門家報酬の相場を見て、「うわ、結構高いな…」と感じられたかもしれません。もちろん、時間と熱意さえあれば、相続税の申告(税理士業務)以外の手続きの多くは、ご自身で行うことも可能です。
しかし、私たちFPの視点から見ると、「目先の報酬を節約した結果、時間や労力、さらには家族関係という、もっと大切なものを失ってしまった」というケースも少なくありません。
この章では、「自分でやる」場合のリアルと、「専門家に頼む」場合の判断基準を明確にします。
「自分でやる」場合のリアル(時間・労力・精神的コスト)
- メリット
- 4章で挙げた「専門家報酬」が丸ごと節約できます。これが最大のメリットです。
- 4章で挙げた「専門家報酬」が丸ごと節約できます。これが最大のメリットです。
- デメリット(乗り越えるべき壁)
- ① 平日の日中に動く必要がある
役所(戸籍収集)、法務局(登記)、金融機関(預金解約)の窓口は、基本的に平日の日中(9時~17時)しか開いていません。お仕事をされている方にとって、これが最大のハードルとなります。 - ② 膨大な時間と手間がかかる
H3で解説した「出生から死亡までの戸籍集め」や、金融機関ごとに異なる手続き書類の準備など、慣れない作業に膨大な時間が取られます。 - ③ 精神的なストレス
手続きの不備で何度も窓口を行き来したり、疎遠な相続人に連絡を取って実印をお願いしたり…といった作業は、かなりの精神的ストレスがかかります。 - ④ ミスによるリスク
H1で解説した期限(特に相続放棄や相続税申告)を万が一見逃したり、遺産分割協議書に不備があったりすると、法的なリスクや家族間のトラブルに発展する可能性があります。
- ① 平日の日中に動く必要がある
【FP推奨】以下1つでも当てはまれば専門家への相談を
では、どのような場合に専門家を頼るべきか。
私たち「親子で備える相続準備ナビ」が、これまで数多くのご家庭を見てきた経験から、「こういう方は専門家に相談した方が、結果的に安く・早くなりますよ」という判断基準をお伝えします。
以下の項目に1つでも当てはまれば、まずは専門家(特に司法書士や税理士)の無料相談などを活用してみることを強く推奨します。
- 財産に不動産(実家、土地など)が含まれる
- 理由:H1で解説した通り、相続登記が3年以内に義務化されたため、この手続きは避けて通れません。相続登記は専門知識(H4の登録免許税計算など)が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。どうせ最後は頼むなら、面倒な戸籍収集(H3)なども含めて最初から任せてしまった方が効率的です。
- 理由:H1で解説した通り、相続登記が3年以内に義務化されたため、この手続きは避けて通れません。相続登記は専門知識(H4の登録免許税計算など)が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。どうせ最後は頼むなら、面倒な戸籍収集(H3)なども含めて最初から任せてしまった方が効率的です。
- 財産の全容がわからない、または借金があるかもしれない
- 理由:相続放棄(H1)の3ヶ月期限は待ってくれません。財産調査(預金、不動産、借金)を自分だけで行うのが不安な場合、専門家に依頼して迅速に調査を進めないと、借金を背負うリスクを負うことになります。
- 理由:相続放棄(H1)の3ヶ月期限は待ってくれません。財産調査(預金、不動産、借金)を自分だけで行うのが不安な場合、専門家に依頼して迅速に調査を進めないと、借金を背負うリスクを負うことになります。
- 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる
- 理由:相続人が多いほど、戸籍集めは膨大になります。また、疎遠な方(例えば、前妻の子や、ほとんど付き合いのない兄弟姉妹など)にご自身で連絡を取り、遺産分割協議や実印のお願いをするのは、精神的に非常に困難です。プロが第三者として間に入るだけで、スムーズに進むケースは非常に多いです。
- 理由:相続人が多いほど、戸籍集めは膨大になります。また、疎遠な方(例えば、前妻の子や、ほとんど付き合いのない兄弟姉妹など)にご自身で連絡を取り、遺産分割協議や実印のお願いをするのは、精神的に非常に困難です。プロが第三者として間に入るだけで、スムーズに進むケースは非常に多いです。
- 平日に役所や銀行に行く時間がない
- 理由:「自分でやる」場合の最大のハードルがこれです。「平日に何度も休めない」という方は、時間をお金で買う(専門家に依頼する)という割り切りが賢明です。
- 理由:「自分でやる」場合の最大のハードルがこれです。「平日に何度も休めない」という方は、時間をお金で買う(専門家に依頼する)という割り切りが賢明です。
- 相続人同士で揉めそう、または既に揉めている
- 理由:これは即、弁護士に相談すべきケースです。他の専門家は「揉め事の交渉代理」はできません。
「相続手続き代行パック」のメリットと注意点
最近では、司法書士事務所や銀行(信託銀行)が、「戸籍収集から預金解約、不動産登記まで」をセットにした「遺産整理業務」「相続手続き代行パック」を提供しています。
- メリット:窓口が一本化され、相続人がやることは「ほぼ待っているだけ」になるため、時間的・精神的コストはゼロに近くなります。
- 注意点:費用は高額(30万円~)になる傾向があります。また、「どこまでの手続き」がパック料金に含まれているのか(例:相続税申告は別料金か、不動産が複数あっても追加料金なしか)を、契約前にしっかり確認する必要があります。
ご自身の「時間」「知識」「財産状況」「家族関係」を棚卸しして、最適な方法を選んでいきましょう。
【当サイト独自】揉めずに円満相続を終え、次の世代にバトンを渡す秘訣
手続きの流れや書類、費用がわかっても、相続で一番不安なのは、やはり「家族間で揉めてしまわないか」ということではないでしょうか。
私たち保険代理店FPは、弁護士や税理士といった他の専門家とは少し違う視点を持っています。それは、「税金を計算して終わり」「登記をして終わり」ではなく、その後のご家族の生活(キャッシュフロー)や、次の世代への資産承継(二次相続)まで見据えるという視点です。
数多くの相続をお手伝いしてきた私たちが断言する、「円満相続」のための3つの秘訣をお伝えします。
秘訣1:『財産目録』はガラス張りに。特に「保険金」と「生前贈与」
相続が「争続」になってしまう最大の原因は、「隠し事」や「不公平感」から生まれる「不信感」です。
特に注意すべきは、預貯金や不動産といった分かりやすい財産だけではありません。
- ① 生命保険金
- 故人がかけていた死亡保険金は、原則として「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象にはなりません(例:長男が受取人なら、長男だけのもの)。
- しかし、他の相続人から見れば「長男だけが多額のお金をもらってズルい」という不公平感の火種に、実によくなりやすいのです。
- ② 生前贈与(特別受益)
- 「長男は家を買う時に親から1,000万円援助してもらった」「次女は留学費用を全部出してもらった」といった、生前の特別な援助(これを特別受益といいます)も、不公平感の原因です。
これらを隠したまま遺産分割(残った財産の分け方)の話を進めようとすると、「知らなかった」「不公平だ」と必ず揉めます。
保険金や生前贈与も含めた「全ての財産情報」を一覧(財産目録)にし、「まずは全体像を把握しましょう」とガラス張りにすることが、信頼関係の第一歩です。
秘訣2:「寄与分」より「感謝」を伝える(感情論の回避)
遺産分割協議でよく出てくる言葉に「寄与分(きよぶん)」があります。これは、「私は長年、親の介護を一身に引き受けてきたから、その分、財産を多くもらう権利がある」と主張するようなものです。
もちろん、法律的にも認められる権利です。
しかし、お金の話の前に、「お義姉さん(お兄さん)がずっとお母さんの面倒を見てくれたおかげで、本当に助かった。ありがとう」という感謝の言葉が他の相続人からあるかどうかで、その後の話し合いの空気は180度変わります。
介護の苦労はお金に換算できるものではありませんし、他の相続人も「自分は何もできなかった」という罪悪感を抱えているかもしれません。
法律(権利)の話と、家族の感情(感謝・ねぎらい)の話を、ゴチャ混ぜにしないこと。これが、30~40代の「調整役」世代に求められる、円満相続のコツかもしれません。
秘訣3:今回の相続(一次)で「二次相続(次の相続)」もシミュレーションする
これが、私たちFPが最も重要視する視点です。
例えば、父が亡くなり(=一次相続)、相続人が母と子2人だったとします。
この時、「お母さんも大変だろうから、財産は全部お母さんが相続しよう」と決めるのは、一見、円満に見えます。
しかし、これが「落とし穴」になることがあります。
- 一次相続:母(配偶者)が相続する分には「配偶者の税額軽減」という強力な特例があり、法定相続分(この例では1/2)または1億6千万円までなら、相続税は0円です。
- 二次相続:しかし、その母が亡くなった時(=二次相続)、母が父から相続した財産も全部含めて、子供たちが相続することになります。二次相続では「配偶者の税額軽減」は使えません。
結果として、「一次相続と二次相続のトータルで払う相続税」で考えると、一次相続で母が全部相続したせいで、二次相続で子供たちが払う税金が、何倍にも跳ね上がるケースがあるのです。
今回の苦労を、あなたのお子さんにさせないために(親子で備える)
あなたが今、この記事を読んで相続手続きの流れを学んでいるように、相続は「知っている」か「知らない」かで、家族関係や納税額が大きく変わってしまいます。
今回の相続(一次相続)を無事に終えることはもちろん大事です。
しかしそれ以上に、今回学んだ「大変さ」や「備えの重要性」を、あなたのお子さんの世代に引き継がせないことこそが重要だと、私たちは考えます。
それが、当サイト「親子で備える相続準備ナビ」の理念でもあるのです。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 遺言書(自筆)を見つけたら、すぐに開封していいですか?
-
いいえ、絶対に勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)を見つけた場合、速やかに家庭裁判所に提出し、「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があります。
もし勝手に開封してしまうと、内容を改ざんしたと疑われたり、5万円以下の過料(罰則)が科されたりする可能性があります。まずは他の相続人に「見つかった」と伝え、冷静に検認の手続きを進めましょう。 - Q2. 故人の預金口座はいつ凍結されますか?葬儀費用はどうする?
-
金融機関は、口座名義人が亡くなった事実を(遺族からの連絡などで)知った時点で、直ちにその口座を凍結します。これにより、預金は一切引き出せなくなります。
葬儀費用など当面の資金が必要な場合は、2019年から始まった「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、遺産分割協議前でも一定額(最大150万円かつ法定相続分の3分の1)を引き出せる可能性があります。まずは金融機関の窓口に相談してみてください。 - Q3. 相続財産が基礎控除以下なら、本当に何もしなくていい?
-
「相続税の申告」は不要ですが、「相続手続き」は必要です。この違いが重要です。本文(H2)でも解説した通り、相続税がかからなくても、故人名義の預貯金を解約したり、不動産の名義を相続人に変更(相続登記)したりする手続きは必ず発生します。特に相続登記は義務化されていますので、「税金ゼロ=何もしなくていい」ではないと覚えておいてください。
- Q4. 相続登記の義務化、放置したらどうなる?罰則は?
-
2024年4月から義務化された相続登記(不動産の名義変更)は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。もし正当な理由(例:相続人間で遺産分割が全くまとまらない、など)がなく、この期限内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
また、名義変更を放置するほど、次の相続(二次相続)が発生して権利関係が複雑になり、将来お子さんたちがもっと大変な思いをすることになります。 - Q5. 相続手続きの費用を安く抑える方法はありますか?
-
あります。一番は、ご自身でできる手続きはご自身でやることです。特に「平日に時間が取れる」方であれば、戸籍収集や金融機関の解約手続きをご自身で行うだけで、専門家報酬を大幅に節約できます。
ただし、不動産(相続登記)がある場合や、相続税がかかる場合は、その部分だけを専門家(司法書士や税理士)にスポットで依頼し、報酬を抑えるのが現実的かつ賢明な方法と言えるでしょう。
まとめ
相続手続きは、まず全体像と期限を把握することから始まります。特に「7日以内(死亡届)」「3ヶ月以内(相続放棄)」「4ヶ月以内(準確定申告)」「10ヶ月以内(相続税申告)」「3年以内(相続登記)」の5大期限は命取りになります。このタイムラインを意識して、やるべきことを整理しましょう。
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×相続人数)により、9割のご家庭で相続税申告は不要です。しかし、「税金ゼロ=手続きゼロ」ではありません。特に2024年から義務化された不動産の名義変更(相続登記)は、相続税がかからなくても必ず3年以内に行う必要があります。
相続手続きで最初につまずくのが、「戸籍謄本の収集(相続人の確定)」と「財産調査(借金含む)」です。これらは「3ヶ月以内」の相続放棄の判断や、その後の遺産分割協議の土台となる非常に重要な作業です。2024年からの広域交付制度(H3)なども活用し、効率的に進めましょう。
相続手続きの費用には「実費」と「専門家報酬」があります。平日に役所や銀行へ行く時間が取れない方、財産に不動産が含まれる(相続登記が必須な)方、相続人間で揉めそうな方は、無理せず司法書士などの専門家に相談する方が、結果的に「安く・早く・確実」に終わるケースが多いです。
手続きを無事に終えるだけでなく、「なぜ揉めたか」「何が大変だったか」を次の世代に伝えることが重要です。今回の相続(一次相続)だけでなく、次の相続(二次相続)まで見据えて遺産分割を行うFPの視点を持つことで、あなたのお子さんたちが将来同じ苦労をしない「円満相続」の準備ができます。