【2025年最新】相続と贈与はどっちが得?5000万円の境界線と「新・精算課税」の賢い選び方

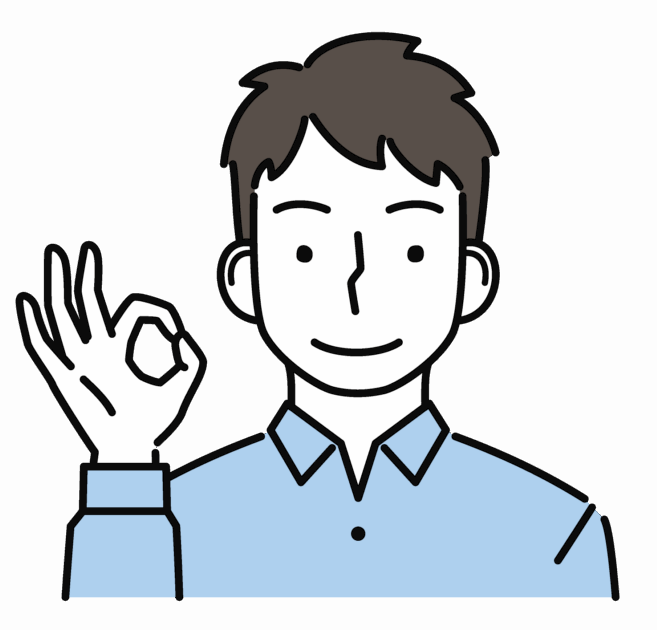
「相続税対策といえば、コツコツ毎年110万円を贈与するアレでしょ?」
もしあなたがそう思っているなら、その知識は少し古くなっているかもしれません。
昨年の税制改正(令和6年)から約2年が経過し、これまでの「相続・贈与の常識」は大きく変わりました。以前は最強とされた「暦年贈与」が、今では状況によって「申告の手間だけかかって効果が薄い」方法になってしまうケースさえあるのです。
特に資産5,000万円前後のご家庭は、判断が非常に難しい「境界線」にいます。
「うちは関係ない」
と放置して二次相続で多額の税金を払うことになるか、あるいは焦って贈与して逆に損をしてしまうか……。
この記事では、最新の法改正実務を熟知したファイナンシャルプランナーが、「新・相続時精算課税制度」vs「暦年贈与」の比較から、具体的な資産5,000万円のシミュレーションまでを徹底解説します。
複雑な計算式は覚える必要はありません。この記事を読み終わる頃には、あなたのご家庭にとって「相続」と「贈与」どちらが得か、自信を持って判断できるようになっているはずです。
2025年現在、相続 vs 贈与の「正解」はこう変わった!
まず単刀直入に結論からお伝えします。「相続(死後に渡す)」と「贈与(生前に渡す)」、どちらが得か?という問いに対する答えは、あなたの「資産規模」と、贈与する親の「年齢(持ち時間)」によって以下の3パターンに明確に分かれます。
- 資産が基礎控除以下(例:5,000万円以下で子が複数)
→ 「何もしない(相続)」が正解。 無理な贈与はコストの無駄です。 - 資産が多く、親が比較的若い(60代〜70代前半)
→ 「新・相続時精算課税制度」を使って、早期に資産を移転させるのが新・王道。 - 資産が多く、相続発生が近い(70代後半〜・健康不安あり)
→ 「孫への暦年贈与」など、加算対象外のルートを使うのが賢明。
なぜ、このように言い切れるのでしょうか?その理由は、2024年のルール変更により「駆け込み贈与」の逃げ道がふさがれ、逆に「早期の計画的贈与」が優遇されるようになったからです。
これまで(2023年以前)は、「亡くなる3年前」までの贈与が相続財産に足し戻されていましたが、現在はその期間が「7年前」まで延長されています。
つまり、亡くなる直前に慌てて子供に暦年贈与を行っても、その多くは相続財産としてカウントされ、節税効果が消滅してしまうのです。
一方で、新しくなった「相続時精算課税制度」には、年110万円の基礎控除が新設されました。
これは申告不要で、万が一の際の持ち戻し(相続財産への加算)もありません。「暦年贈与一択」だった時代は終わり、今は「時間を味方につけられるなら新制度(精算課税)、直前なら孫などの別ルート」という使い分けが、手残りを最大化する唯一の解なのです。
まずは「昔の常識はいったん忘れる」。これが、賢い相続準備のスタートラインです。
基礎知識:相続と贈与、お金が残るのはどっち?(税率の仕組み)
具体的なシミュレーションに入る前に、一つだけ誤解を解いておきましょう。
よく「贈与税は相続税より税率が高いから損だ」という話を耳にしませんか?
確かに、最高税率だけを見れば贈与税の方が高く設定されています。
しかし、資産承継の実務において重要なのは表面的な税率ではなく、「低い税率の枠をどれだけ有効活用できるか」という点です。
相続税と贈与税には、決定的な違いがあります。
- 相続税: 亡くなった時点の「財産総額」に対してドカッとかかる
- 贈与税: もらった時点の「財産単体」に対してその都度かかる
相続税は、資産が積み上がれば積み上がるほど税率が高くなる「超過累進税率」です。
例えば、資産の「上澄み部分」にかかる税率が30%だとします。この部分をそのまま持っていれば、将来30%の相続税がかかります。
しかし、その部分を生前に少しずつ切り崩して贈与すれば、贈与税は「10%」や、基礎控除内であれば「0%」で済むかもしれません。
「どちらが得か?」という問いは、「将来の相続税率と、今の贈与税率、どっちが低い?」という問いと同義なのです。
【徹底シミュレーション】資産5,000万円の「落とし穴」と対策
では、いよいよ本題です。多くのご家庭で現実的なラインとなる「資産5,000万円」を例にシミュレーションしてみましょう。
実は、5,000万円前後の資産は、「一次相続(両親のどちらかが亡くなる)」と「二次相続(残された親も亡くなる)」で、天国と地獄ほど状況が変わる「要注意ゾーン」です。
ケース1:一次相続(父死亡、母と子2人が相続)
- 相続人: 母、長男、長女(計3人)
- 基礎控除額: 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
資産5,000万円に対して基礎控除が4,800万円あるため、課税対象はわずか200万円です。
さらに、配偶者には「法定相続分または1億6,000万円までは無税」という強力な「配偶者の税額軽減」特例があります。これを使えば、相続税は実質0円になるケースがほとんどです。
この段階で焦って生前贈与をする必要性は低いです。むしろ、老後の生活費として手元に残しておく方が賢明でしょう。
ケース2:二次相続(母死亡、子2人が相続)
父から相続した財産と、母自身のへそくりなどを合わせて、母の資産が再び5,000万円ある状態で亡くなったとします。
- 相続人: 長男、長女(計2人)
- 基礎控除額: 3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
相続人が一人減るため、基礎控除の壁が4,200万円に下がります。
5,000万円 - 4,200万円 = 800万円 が課税対象となります。
| 項目 | 何もしなかった場合(相続) | 10年間贈与していた場合 |
| 課税遺産総額 | 800万円 | 0円(基礎控除以下にする) |
| 相続税額(総額) | 約80万円 | 0円 |
| 贈与税額(総額) | 0円 | 0円(非課税枠内) |
| 手残り財産の差 | ▲80万円 | +80万円 |
※概算計算です。諸条件により変動します。
何もしなければ、国に約80万円を納税することになります。「たかが80万」と思うかもしれませんが、これは「知識があれば払わなくて済んだはずのお金」です。
このケースでは、母が元気なうちに「新・相続時精算課税制度」などを活用して、基礎控除(4,200万円)のラインまで資産を子供に移しておけば、税金を完全な「ゼロ」にコントロールすることが可能です。
資産5,000万円クラスの方は、「二次相続」を見据えた時だけ贈与が得をする可能性が高いです。「配偶者がいるうちは安心、一人になったら即対策」と覚えておきましょう。
新旧対決!「暦年贈与」vs「新・相続時精算課税制度」
「シミュレーションで贈与が必要なのはわかったけれど、具体的にどうやればいいの?」
ここで登場するのが、2024年の改正で大きくパワーアップした「新・相続時精算課税制度」です。
これまで(2023年以前)は、「暦年贈与(毎年110万円まで非課税)」が王道で、相続時精算課税制度は「一度選ぶと二度と暦年贈与に戻れない」「申告が面倒」といったデメリットがあり、敬遠されがちでした。
しかし、現在はその力関係が逆転しています。以下の比較表をご覧ください。
| 比較項目 | ①暦年贈与(従来型) | ②新・相続時精算課税(新型) |
| 年間の非課税枠 | 110万円 | 110万円(新設!) |
| 申告の手間 | 110万円超なら毎年必要 | 初年度のみ届出(※枠内なら不要) |
| 死亡時の持ち戻し | 死亡前「7年間」分が加算 | 年110万円枠内は加算なし! |
| 誰におすすめ? | 孫・嫁・婿(相続人以外) | 子・孫(まとまった資産移転) |
最大のポイントは、「持ち戻し(加算)」のルールです。
従来の「暦年贈与」は、せっかく贈与しても、親が亡くなる前7年間に贈与された分は「なかったこと」にされ、相続財産に足し戻されて税金がかかります。いつ亡くなるかは誰にも予測できないため、常にリスクがつきまといます。
つまり、親がご高齢(例えば80歳以上)で、「7年も生きられるか不安」という場合でも、この制度を使えば確実に年間110万円ずつ資産を減らすことが可能です。
- 親が60代〜70代前半: 時間的な余裕があるため、どちらを選んでもOKですが、管理が楽なのは「新・相続時精算課税」。
- 親が75歳以上・健康不安あり: 持ち戻しのリスクがない「新・相続時精算課税」が圧倒的に有利。
- 孫への贈与: 相続人ではない孫への暦年贈与は、原則持ち戻し対象外(※遺言等がない場合)。そのため、あえて「暦年贈与」を使うのも有効な戦略。
【決定版】迷いを断つ「相続か贈与か」判断フローチャート
最後に、ここまでの内容を整理し、あなたが今すぐ取るべき行動をフローチャートにしました。これに従って進めば、大きな失敗は防げます。
あなたの家の資産総額は「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)」を超えていますか?
- NO(超えていない): 「何もしない(相続)」でOKです。贈与の手間をかける必要はありません。
- YES(超えている): STEP 2へ進んでください。
資産の多くは「現金・有価証券」ですか? それとも「不動産」ですか?
- 不動産がメイン: 不動産の生前贈与は、登録免許税や不動産取得税が高くつくため、コスト倒れになりがちです。「小規模宅地等の特例」を使って相続での評価減を狙うのが定石です。
- 現金・株がメイン: 贈与がしやすい資産です。STEP 3へ進んでください。
贈与する親の年齢や健康状態はどうですか?
- まだ若い・健康: 「新・相続時精算課税制度」を使って、年間110万円の基礎控除+α(2,500万円の特別控除枠)を使い、計画的に資産を移転させましょう。
- 高齢・体調不安: 暦年贈与は持ち戻しリスクが高いためNG。「新・相続時精算課税」の110万円枠を使うか、教育資金贈与などの特例活用、あるいは生命保険の非課税枠活用を優先してください。
よくある質問とその回答(FAQ)
- Q1. 2024年より前に始めた暦年贈与はどうなりますか?
-
2023年以前に行った贈与については、改正前のルールが適用されます。つまり、持ち戻し期間は「3年」のままです。2024年1月1日以降に行う贈与から、段階的に持ち戻し期間が7年へと延長されていきますので、過去の贈与分について心配する必要はありません。過去の対策は有効ですのでご安心ください。
- Q2. 新しい精算課税制度を選んだ後、暦年贈与に戻せますか?
-
いいえ、戻せません。一度「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出すると、その贈与者(親)からの贈与については、一生涯その制度が適用されます。「やっぱり暦年贈与の方が良かった」と後悔しても撤回できないため、選択する際は慎重な判断が必要です。ただし、父は精算課税、母は暦年贈与といった使い分けは可能です。
- Q3. 贈与契約書は毎回作らないとダメですか?
-
はい、作成を強く推奨します。法律上は口頭でも契約は成立しますが、税務調査が入った際、単なる「名義預金(親が勝手に子の口座に入れただけ)」と疑われないための最も強力な証拠が贈与契約書です。大学ノートの切れ端でも有効ですが、日付、金額、双方の署名・捺印が必須です。今は電子契約で安価に残す方法も一般的です。
- Q4. 専業主婦の妻の「へそくり」は贈与になりますか?
-
夫の給料から生活費をやりくりして貯めた「へそくり」は、実質的に夫の財産とみなされる可能性が高いです。これを妻名義の口座に入れておくと、夫が亡くなった際に「夫の相続財産」として課税対象になったり、逆に妻が先に亡くなった際に夫へ「贈与」されたとみなされるリスクがあります。金額が大きい場合は、正式に贈与契約を結んでおくことが安全です。
- Q5. 生命保険と贈与、まずはどっちをやるべき?
-
優先順位は「生命保険」が先です。生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、現金を保険に変えるだけで即座に評価額を下げられます。面倒な申告も不要で、受取人を指定できるため遺産分割トラブルも防げます。まずは保険の非課税枠を使い切り、それでも資産が溢れる場合に贈与を検討するのが鉄則です。
まとめ
資産5,000万円が「判断の境界線」であると知る
基礎控除ギリギリのラインである5,000万円層は、配偶者がいる一次相続では税金がかからないことが多いですが、片親になる二次相続で課税されるリスクが高まります。この「将来のリスク」を見越して動くことが重要です。
2024年以降は「新・相続時精算課税」が有力な選択肢
法改正により、年110万円の基礎控除が新設され、持ち戻し(相続財産への加算)がないという強力なメリットが生まれました。従来の「暦年贈与一択」という常識を捨て、新制度の活用を前向きに検討してください。
「孫」への贈与は依然として有効な節税策
相続人ではない「孫」への暦年贈与は、原則として持ち戻しの対象外です(※例外あり)。親の年齢が高く、駆け込みでの対策が必要な場合、孫への贈与は資産を減らすための非常に有効な手段となります。
不動産や生命保険の活用も忘れずに
贈与だけが対策ではありません。現金を不動産に変えたり、生命保険の非課税枠を使ったりすることで、資産の評価額そのものを下げることが可能です。贈与を実行する前に、まずはこれらの「資産組み換え」が完了しているか確認しましょう。
迷ったら自己判断せず専門家へ相談を
相続税対策は、家族構成や資産状況によって「最適解」が180度変わります。良かれと思ってやった贈与が、かえって税金を高くしてしまうこともあります。実行する前に一度、相続に強いFPや税理士のセカンドオピニオンを受けることを強くお勧めします。